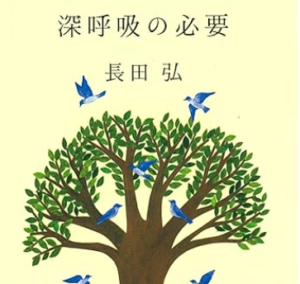「深呼吸の必要」は、2004年に製作された日本映画です。監督は篠原哲雄。主な出演者は、香里奈、谷原章介、成宮寛貴、長澤まさみ。
舞台は沖縄のサトウキビ畑。サトウキビ畑に、期日までにサトウキビの収穫を終わらせるため、若者たちがアルバイト「キビ刈隊」として集められるという設定です。
この映画の存在は前から知っていましたが、映画のタイトルと設定を知れば、もう内容が透けて見えるような気がして、これまで未見だったのです。
ところが、実際に見てみると、最初は「ふむふむ」という感じで、さほど集中していなかったのですが、時間が進むにつれて、次第にフィルムの中に吸い寄せられてゆきました。
私は山梨でしたが、農作業のアルバイトを住み込みでしたことがあり、その頃を想い出したので、映画にのめり込めたのでしょうか。
どうやら、そういうことではないらしい。
役者さんたちは、今もテレビドラマに出演している人気者ぞろいです。どうしてキャストが豪華なのかというと、日本航空が沖縄キャンペーンを展開しためらしいです。
しかし、映画のテイストは単館系のそれを想わせ、最後まで純度を保ったまま映画は終わります。あざとい商業色に汚染されてはいませんでした。
予想していたのとほぼ同じストーリー展開であったにもかかわらず、予想をはるかに超えて楽しむことができました。かなり前ですが、ビデオレンタル店に必ずあった「邦画あなどりがたし」というコーナーを想い出しました。
「深呼吸の必要」のクオリティが邦画の基本水準というぐらいになれば、日本映画を見限る人はいなくなるのではないでしょうか。
それはともかく、この映画のタイトルどおり、今の私は深呼吸が必要です。「深呼吸の必要」は、長田弘という現代詩人の詩集「深呼吸の必要」からとったとか。
この機会に、長田弘の詩集も読んでみようと思っています。