Views: 106
室生犀星の以下の詩を知らない人は、まずいないと思いますが、いかがでしょうか?
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食となるとても
帰るところにあるまじや
この詩の題名は「小景異情(その二)」。詩集「抒情小曲集」(大正6年9月)に収められています。
多くの人は、上の五行だけを暗唱しているのではないでしょうか。
「異土」は「いど」と読み、「故郷以外の土地。異郷」という意味。「乞食」は「かたい」と読み、「乞食(こじき)」と同じ意味。
それにしても、哀しい歌ですね。私、風花未来は、ふるさとを持ち、そして、ふるさとに帰れないほど、辛いことはありません。私は18歳で東京に出て以来、ずっと故郷である浜松を避けていた気がします。しかし、父親の具合が悪くなったこともあり、帰郷して5年ほど生活。現在は、また引っ越して埼玉に住んでいます。
郷里に帰った時は、ふるさとのことをしきりに想っている、そんな毎日がずっと続いているのでした。
そして私はまた故郷から旅立ったのですね。「悲しくうたふ」かどうかは別にして、私もまた「ふるさとは遠きにありて思ふもの」であることを痛感しました。
ふるさとは実際に帰るところではなく、異郷にて、想い出すところであるべきだと私自身は思っています。これはあくまで私個人の主観です。
再び生まれ故郷を離れようとした時、私は「旅人」になろうと思いました。「人生は旅である」という思いが強くなっていたのですね。
リュックひとつ背負って、全国を放浪したい、そんな気持ちを抑えられなくなっているのでした。
ところで、あの萩原朔太郎も高く評価した「抒情小曲集」に収められた、この「小景異情(その二)」は、東京にいて望郷の想いを歌った詩ではありません。
「小景異情」は六篇あるのですが、すべて郷里である金沢で詠じられた作品です。
室生犀星の郷里は金沢市。そこに帰ったけれど受け入れてもらえず、辛い思いを抱きつつ故郷を去ろうとする時の心情を、室生犀星は詩にしたのでした。
ふるさとは恋しい、でも、事情から帰ることができない(そこに住んで幸せに暮らすことはできない)……そういう人は多いでしょう。また、同じ経験はなくても、容易に想像できる心情だと言えます。
この「ふるさとは遠きありて思うふもの」の詩が愛される理由はそこにあります。
室生犀星のことを良く知っていた萩原朔太郎は、この「ふるさとは遠きにありて思ふもの」の詩を、誤解していたと伝えられます。
その指摘をしているのは山本健吉です。その著書「こころのうた」の中で以下のように見解を述べています。
この詩については、一つの誤解がなされている。それはこれを、都会に零落放浪したころの作だというのである。その誤解が、もっとも犀星の詩と人とを知る友である萩原朔太郎によってなされた。
実際は室生犀星はふるさと金沢でこの詩を書いたのですが、つまり、これから東京に帰ろうと思いながら書いたわけです。
しかし、萩原朔太郎は、室生犀星は遠い地から金沢を想って詠じた、と解釈してしまった。犀星の郷里が農村ではなく、金沢市であるから「都」と言ったのだと、苦しい説明をしている、と山本健吉は語っています。
また、詩の評論で定評のある伊藤新吉も、「現代詩の鑑賞(上)」で以下のように解説しています。
これは東京から郷里に帰っていて、ふたたび東京へむけて旅立つときの感傷だった。
一見しただけでは、東京で作ったのか郷里で作ったのか分かりにくいようだけれども、しかしそれは郷里を離れようとする時の別れの心と、もはや再び帰らぬという決意を歌ったものである。
しかしながら、抒情小曲集にある「ふるさとは遠きにありて思ふもの」の詩を、室生犀星がどの地にいて歌ったかは、この詩を鑑賞する者にとっては、それほど大きな問題ではないと私は思います。
これから東京に帰ろうとしているのか、放浪の地から金沢を想っているのか、それがどちらであっても、この「ふるさとは遠きにありて」の詩から受ける感動に差異はありません。
ひりつくほどの切ない故郷への思い、それは誰もが想像しうる感情だからです。ふつうに読み、ふつうに感動して良い名作、それが「ふるさとは遠きにありて思ふもの」にほかなりません。
どうしても、詩の背景、室生犀星の人生について知りたい人は、以下の伊藤新吉の解説は参考になるでしょう。
わかい日の犀星は、複雑な家庭の事情のためはやくから人の世の孤独を知り、貧しさのくるしみを噛み、愛情の飢えになやんだ。次いで上京してからはいくたびか郷里(金沢市)とのあいだを往復し、東京の町々を放浪した。数多くの抒情小曲は、このような生活から生まれたのである。
やはり最後に「小景異情(その二)」の全文を引用しておきますね。
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食となるとても
帰るところにあるまじや
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひ涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこにかへらばや
遠きみやこにかへらばや
「帰るところにあるまじや」以降を読むと、誤解が生じるのは当然だと言えます。
ところが、一般の人の多くは「帰るところにあるまじや」までしか覚えていないので、素直に感動しているのですね。
「ひとり都のゆふぐれに」の「都」という表現が誤解を生みやすいのでしょう。「ひとりゆふぐれに」にして、「遠きみやこにかへらばや」を「遠い東京(みやこ)に帰へらばや」とすれば、誰も解釈を間違えなかったでしょう。
ただ、それですと、説明的になり過ぎるのは言うまでもありません。
ですから、全文を味わうためには、この「ふるさとは遠きにありて」の詩は「室生犀星は郷里の金沢にいて東京に帰ろうとする時に詠んだ詩である」という予備知識は必要だと言えます。
最初の五行だけで、充分に感動できると私は思うのですが、いかがでしょうか。
詩は最初から最後まで、全体を愛さなければいけないというルールはありません。その一部だけを、愛唱するのも正当な詩の楽しみ方です。
例えば、山村暮鳥の「風景」という詩にも、同じことが言えます。
この詩です⇒山村暮鳥の詩「いちめんのなのはな」の感動を純粋化する方法
あなたは、どのように感じますか?
なお、その他の室生犀星の詩は、以下のページで取り上げています。

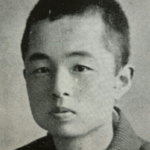

うたの解釈が違います。
このうたは、遠方から故郷を懐かしむうたではありません。
ご指摘、ありがとうございます。
誤解を生みやすい点なので、加筆修正いたしました。
ご参考になれば幸いです。
素晴らしい解説ありがとうございます。親父も大好きなこの歌の本当の意味を誤解していました。
久し振りにこの歌を噛み締めながらお恥ずかしい社会批判を繰り広げています。偉そうな事を言ってもその程度です。何もしないで取り澄ます事も出来ないで恥を晒しています。今、何処の空でどんな事を感じていますか?是非聞かせて下さい。今年は豊川の桜淵の桜を見たい。家代の桜並木を見てみたい。そんな願望に駆られています。
生まれた地を離れた事の無い人は、これをどう思うのか。よく事業に失敗して田舎に引っ込む事があります。うらぶれて、、
人はそれぞれ、うらぶれても、故郷でやり直せば良いじゃない。て、そんな想いの人もいる。
苦しい時代の金沢に帰郷したが、変わらぬ故郷に心痛め、我が心に描く故郷を思う時思わず涙が出てしまう
やはり遠い東京に帰らなくてはいけないんだろうな、と言う故郷金沢に未練を残した切なくやるせない気持ちを表現したものと、愚かな私は理解して口ずさんでいます。
ことのは様 くーちゃん様 心に沁みるお話、ありがとうございます。
世の中には同じ思いの方が居ることに嬉しくなりました。
飾らずに本音を語られるお二方のようになりたい爺さんです。
九州のある離島の高齢の母の元へ帰った長男である夫は、ある日この詩を口ずさみました。そして10月26日午前三時に100才近い母親より先に旅立ちました。私は側にいられなかった。 涙が止まりません。
私は地元のから出た事がありません。結婚を機に退職したのですが
それから家業の食堂を手伝うようになりました。3歳離れた弟がいるのですが、若い頃やんちゃをしていた弟です。それもあり地元を離れていたのですが、母の病気をしその看病の為に帰ってきました。久しぶりに会ってあまり成長していない弟
あなたは何のために帰ってきたの、
故郷は遠きにありて、思うもの
中学校を卒業して、家業を継いで商売を続け30年、地元に生活して、たまに元中学校の同窓生を見かける事があります、それを知りたい人が教えろ教えろと尋ねられても、?
遠方の方程、興味深いようです♪
故郷は遠きにありて---
この詩にひかれます。よしやうらぶれていどのかたいとなるとてもかえるところにあるまじや
歳と共に帰郷の念が強まる。
60年も前の生活が懐かしい。そんな生活なんて今はない。でも、再現しての晴耕雨読を…と憧れる。
思いはそれぞれ違う。
「早く引き上げて帰っておいで!」
「田舎なんて何もないよ。今からでも都会に戻りたいよ。時々、帰るだけでいいじゃない。」
2つの感想に分かれた。
墓石が草の中に埋もれた墓を手伝ってもらいながら二日かけて元通りにした。10年ぶりの帰省をして、ふと浮かんだ(ふるさとは遠くにありて…)が浮かんだ。全体を始めて読んだ。目からウロコだったが、納得。
今、私は…二つの選択肢の中にありつつ…変わらない想いを抱えている。
金沢駅前出身の都内上京組です。子供の頃から馴染みがある詞で彼は私と同じ小将町中学卒でしたね。校歌作詞もされ1番素敵です。私は事業に成功したので都内が終の住処となりました。多くの友人は田舎に帰り残ってのは私ひとりで寂しいです。生き馬の目を抜く都内に住み続けるのは何より経済力が必要ですから。
なんで帰省してはいけないのだろう。
そんな理屈言わんで、いつでも、また帰っておいで。
君の愛する故郷ではないか。
あの道もこの川も、温かい風、優しい空。楽しもうよ。
帰るところではないなんて、悲しくて泣けてしまう。