カテゴリー:美しい詩

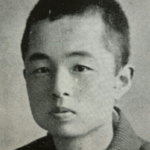
2025/10/31
今日は八木重吉の「みんなも呼びな」という詩をご紹介します。みんなも呼びなさてあかんぼはなぜに、あん、あん、あん、あんなくんだろうかほんとにうるせいよあん、あん、 ...

2025/03/11
映画「気まぐれ天使」で合唱される讃美歌の詩が素晴らしいので、ご紹介します。⇒映画「気まぐれ天使」は、こちらで視聴可能です1:02:19から合唱が始まりますので、 ...
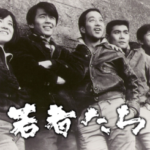
2025/02/05
連続テレビドラマ「若者たち」の第17話「友だち」で朗読された詩をご紹介する。この作者はハインリヒ・ハイネ。尾上柴舟(おのえさいしゅう )によって翻訳された『ハイ ...
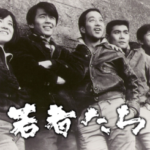
2025/02/05
テレビドラマ「若者たち」の第16話「五月の風の中」で暗唱される詩が実に良いので、ご紹介しよう。題名はドラマ中では明かしていないので、ここでは仮に「五月の風の中」 ...




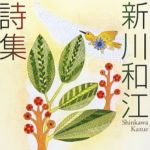


2024/03/16
吉野弘の「Iwasborn」という詩をご紹介。Iwasborn確か英語を習い始めて間もない頃だ。或る夏の宵。父と一緒に寺の境内を歩いてゆくと青い夕靄の奥から浮き ...
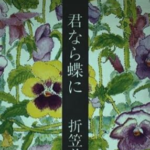
2024/03/14
折笠美秋(おりがさびしゅう)の俳句をご紹介。折笠美秋は、1934年〈昭和9年〉12月23日に生まれ、1990年〈平成2年〉3月17日に死去した。俳人、新聞記者。 ...
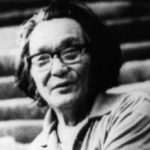

2024/03/12
今回は田中克己(たなかかつみ)の短歌をご紹介。「詩集西康省」の序の歌この道を泣きつつ我の行きしこと我がわすれなばたれか知るらむこの短歌は予備知識は一切必要ない。 ...