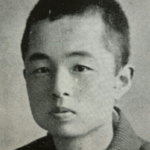Views: 70
今回は島崎藤村の「小諸なる古城のほとり」という詩をご紹介します。
島崎藤村は「若菜集」「一葉舟」「夏草」「落梅集」という4冊の詩集を出版。この「小諸なる古城のほとり」は「落梅集」に収められています。
「小諸なる古城のほとり」が最初に発表されたのは1890年(明治33年)で、雑誌「明星」に掲載されました。その時の題名は「旅情」でした。
では、さっそく、「小諸なる古城のほとり」の全文を引用してみましょう。
小諸なる古城のほとり
小諸なる古城のほとり
雲白く遊子(いうし)悲しむ
緑なす蘩蔞(はこべ)は萌えず
若草も藉(し)くによしなし
しろがねの衾(ふすま)の岡辺(おかべ)
日に溶けて淡雪流る
あたゝかき光はあれど
野に満つる香(かをり)も知らず
浅くのみ春は霞みて
麦の色わづかに青し
旅人の群はいくつか
畠中の道を急ぎぬ
暮行けば浅間も見えず
歌哀し佐久の草笛
千曲川いざよふ波の
岸近き宿にのぼりつ
濁(にご)り酒濁れる飲みて
草枕しばし慰む
前に取り上げました「潮音」と違って、「小諸なる古城のほとり」には固有名詞が出てきます。
「小諸」「浅間」「佐久」「千曲川」という固有名詞によって、この詩の舞台をある程度はイメージできるでしょう。
島崎藤村は1899年(明治32年) 小諸義塾の英語教師として長野県北佐久郡小諸町に赴任。以後6年、小諸町で過ごすしました。この時期を文学史的には「小諸時代」と呼ばれています。この時期に藤村は冬子と結婚。長女みどりも生まれました。
小諸を中心とした千曲川流域の人びとの暮らしと自然を写生した随筆「千曲川のスケッチ」は、この「小諸なる古城のほとり」の注釈としても読むと興味深いでしょう。
「小諸なる古城のほとり」は、藤村が小諸にきて二年目の初春に作られました。1890年(明治33年)、藤村は当時29歳でした。
小諸時代に、藤村は詩から小説に転身。有名な小説「破戒」も、この頃に書き始められました。
明治の詩ですから、さすがに読みにくい字、意味が取りにくい言葉があります。そこで、今回は少し注釈を加えてみることにしました。
●「遊子」は原作には「いうし」とフリガナがふられていますが、現代仮名遣いでは「ゆうし」と書きます。旅人のことです。
●「蘩蔞」は「はこべ」と読み、春の七草の一つ。
●「若草も藉(し)くによしなし」は「腰をおろして休むには、若草はまだそれほど伸びていない」くらいの意。
●「衾」は「ふすま」と読み、夜具、ふとんの意。
●「野に満つる香(かをり)も知らず」は「野辺にはまだ若々しい春の息吹は感じられない」くらいの意。
●「佐久」は「さく」と読み、小諸一帯の地名。
●「濁り酒」は、ふつうは「どぶろく」を指すが、ここでは「地酒」。
●「草枕」は「くさまくら」と読み、旅情、旅愁の意。
厳密には、意味が取れなくても、全体の流れの中でイメージがつかめれば充分だと思います。
「潮音」とは異なり、物寂しい抒情が漂っていますね。
三好達治は藤村の「小諸なる古城のほとり」を、明快に評しています。
「緑なす蘩蔞」「若草」「野に満る香」などの春のイメージが、藤村みずからが提示しておきながら、それらをことごとく否定しているところに、この詩の形式の特徴がある。またそれが哀切な詩情をかもしている、と三好達治はいうわけです。