Views: 42
久しぶりに、石川啄木の歌集を読み始めました。今は「一握の砂」を中心に読んでいます。
意外な発見があり、またいろいろと思うことがありましたので、それについて書きとめておきます。
今回私が読んでいるのは、旺文社の以下の文庫本です。
すでに絶版となっておりますが、中身はかなり充実しています。与謝野晶子と若山牧水の追悼文が掲載されているのも貴重でしょう。
石川啄木の生涯は、わずか26年。
詩人は夭折する人が少なくないのですが、石川啄木はたったの26年でその生涯を閉じました。金子みすゞも26歳で夭逝していますね。
石川啄木の極貧生活は有名ですし、一家離散も経験していて、彼の生涯は決して幸福ではなかったと、若い頃からイメージしてきました。
しかし、臨終の際に、若山牧水と文学談義をしていたという話(若山牧水の追悼文にある)を読んでみて、石川啄木の生涯は決して不幸ではなかったと強く思ったのです。
生きた時間は短かったけれども、頭の天辺からつま先まで、臨終の際まで文学の夢で詰まっていた。しかも、感性のみずみずしさが頂点である状態で歌い切れたのは、むしろ幸福であったと言えるのではないでしょうか。
医学の進歩した現代ならはもっと長生きできたとも言えます。しかし、今のように高度情報化社会の中で、石川啄木が自身の純粋な詩魂を純粋なままに保持できたとはとても思えません。
石川啄木という生き方について。
石川啄木の生き方は、破滅型というか、処世術というものまるで知らなかった。だから、あのような特異な歌が歌えたのでしょう。
石川啄木についていろいろと考えているうちに、表現の原点についてにまで思い至りました。
大量に出版される現代の本のほとんどに私が共感できないのは、著者が自分を安全地帯(安全な場所)において言葉を発しているからだと、石川啄木歌集が私に教えてくれました。
石川啄木は、愚直なまでに、自分の感覚に忠実だったことが、彼の歌集を読めばわかります。
時に、愚かさを感じるほど無防備に人生に立ち向かい、苦悩だけでなく、矛盾や感傷にまで正直であろうとした啄木に、今の私は惹かれます。
啄木の天才は「歌の過剰性」にある。
啄木の歌を読むと、やはり啄木は天才だったという思いを新たにしました。
リアルな生活の写生からは乖離してしまうほど、啄木は自分の「天才」、即ち「歌の過剰」に苦しんでいたと私は推測しています。
天賦の才があるために、自分の思いより先に、歌の方が生まれてしまった、というふうなことを私に感じさせるのは、石川啄木しかいません。
そこが若山牧水と啄木との違いだと思います。若山牧水の歌は牧水の生活を鏡のように映していた。
一方、啄木の歌は彼自身の生活そのものではなく、そこには虚構があるのは確かでしょう。
しかし、啄木のイマジネーションは、単なる絵空事ではなく、短歌となって人間の心の核心を哀しいまでについてくるので、多くの人たちに共感されるのかもしれません。
そうした「歌の過剰」にこそ、啄木の歌の特性が存するのでしょうね。
実は、啄木の悲劇であったとも私は思うのですが、それについては、また機会があれば書いてみたいと思います。
石川啄木の代表的な短歌
知ってはいても、読み返す機会がほとんどないという方のために、以下で、石川啄木の代表作と思われる短歌をご紹介しておきます。
東海の小島の磯の白砂に
われ泣きぬれて
蟹とたはむる
いのちなき砂のかなしさよ
さらさらと
握れば指の間より落つ
たはむれに母をい背負ひて
そのあまり軽きに泣きて
三歩あゆまず
こころよく
我にはたらく仕事あれ
それを仕遂げて死なむと思ふ
はたらけど
はたらけど猶わが生活楽にならざり
ぢつと手を見る
やはらかに柳あをめる
北上の岸辺目に見ゆ
泣けとごとくに
ふるさとに訛(なまり)なつかし
停車場の人ごみの中に
そを聴きにゆく
不来方(こずかた)のお城の草に寝ころびて
空に吸われし
十五の心
飴(あめ)売りのチャルメラ聴けば
うしないし
をさなき心ひろへるごとし
友がみなわれよりえらく見ゆる日よ
花を買ひ来て
妻としたしむ
恋愛短歌は別ページでまとめてみましたので、こちらをご覧ください⇒石川啄木の恋愛短歌


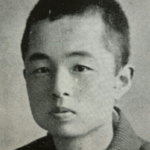

大変面白い記事で楽しませていただきました。
私は「団塊世代の我楽多(がらくた)帳」(https:skawa68.com)というブログの
2019/9/22付けで「石川啄木」の記事投稿
しています。つたない記事ですが、もし、ご参考にしていただければ幸いです。
とてもすごい。
本当に「詩」というものを初めて知った作者の人です。
ありがとうございます!!