Views: 48
はかない命を歌いつつも、その歌そのものは、永遠の命を得ている……そんな奇跡のような短歌があります。現代的な感覚にもマッチするので、短歌というよりも一行詩と呼んだ方が良いかもしれません。
世のなかに光も立てず星屑の落ちては消ゆるあはれ星屑
あの有名な純愛小説「野菊の墓」の作者である、伊藤左千夫の短歌です。
複雑なことは歌っていませんね。はかない命を、光ることもなく消えてゆく星にたとえることで象徴的に詠じています。
「世のなかに」という一語で、空を流れる星のことを歌っていないのがわかります。星そのものを歌うとしたら「この宇宙で」となるはずです。
この歌を私がどこで知ったかをお伝えすると、この短歌の意味がさらにわかりやすくなるかと思います。
映画の中の登場人物が朗読する短歌のひとつが、上の歌でした。その映画は木下恵介が1955年に監督した「野菊の如き君なりき」です。
伊藤左千夫の「野菊の墓」を映画化した作品で、この映画も歴史に残る名作。
伊藤左千夫の短歌「世のなかに光も立てず星屑の落ちては消ゆるあはれ星屑」は映画の中で朗読されますが、この短歌だけが強調されているわけではありません。しかし、主人公である2人の悲恋を見事に象徴していると感じ、私にとって一生忘れられない歌となりました。
映画「野菊の如き君なりき」は、老人が昔を回想するという設定になっていまして、その老人を演じたのが名優・笠智衆でした。笠智衆の短歌の読みあげ方も渋くて、それだけでも涙を催すほどです。
これから「野菊の如き君なりき」をご覧になる方は、「世のなかに光も立てず星屑の落ちては消ゆるあはれ星屑」を笠智衆が朗読するシーンに、どうかご注目ください。
1950年代は日本映画の黄金期で、この時代の映画を繰り返し味わえるだけでも、日本人に生まれて良かったと心底思います。
小説「野菊の墓」では、15歳の少年・斎藤政夫と2歳年上の従姉・民子とのはかない恋が描かれます。星屑の歌は、伊藤左千夫自身の実らなかった恋のはかなさを歌った作品だと解釈して間違いはないでしょう。
最初にこの短歌に出逢った時のことを想い出しますと、今でも胸の奥が切なくなります。
光らぬ星くずを歌っているにもかかわらず、胸にすうーっと一筋の光が流れてゆくのが感じられたのです。
あの時は、私はたぶん、若い男女の悲恋を詠んだ短歌というより、もっと根源的な人間の魂の哀しみ、存在そのもののはかなさに、心を震わせていたのでしょう。
そして、今もう一度、この「世のなかに光も立てず星屑の落ちては消ゆるあはれ星屑」を読みかえしてみますと、新たな感慨が浮かんでくるのでした。
原作小説「野菊の墓」も、映画「野菊の如き君なりき」も、日本人的な抒情が表出されていて、その抒情の純度の高さ以外に芸術的な価値はありえないとさえ思っておりました。
しかし、星くずの歌を、今復唱してみますと、哲学的、概念的なことは、語っていない作品ですが、その背後というか、奥に、人生的な深い示唆が含まれていると思われてなりません。
光らず消えてゆく無数の星がある。星は人に見られた時にその輝きを示すのであって、決して光っていないわけではなく、どの星も精一杯光を放って生きているのだ。恋はかなわなかったが、精一杯、愛したことは誠であり、その愛は永遠の光の帯となって魂に刻まれている……
「野菊の墓」の伊藤左千夫と「野菊の如き君なりき」の木下恵介が、意図したことはわかりません。ただ、この時代を生きてゆく私にっとって、決して時代遅れの旧作ではなく、郷愁の破片でもなく、新たな示唆と光を与えてくれる貴重な作品だと断言したいのです。
そして、星くずの歌は、未来への静かな讃歌として、新たに胸に刻みたいと思っています。

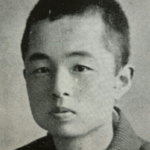

愛を貫く。恋が叶わなかった。
本当に、愛を貫いたら後悔は残らないと思います。
これが、削って 削っての世界感にも通じる。
愛を貫いたら、捨てていくものの方が、多い。