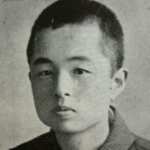Views: 45
今日は八木重吉の「みんなも呼びな」という詩をご紹介します。
みんなも呼びな
さて あかんぼは
なぜに、あん、あん、あん、あん なくんだろうか
ほんとにうるせいよ
あん、あん、あん、あん
あん、あん、あん、あん、
うるさかないよ、うるさかないよ
よんでるんだよ
かみさまをよんでいるんだよ
みんなもよびな
あんなにしつこくよびな
「みんなも呼びな」は、1925年(大正14年6月7日)付けの手稿小詩集「ことば」に収録されている。
以前、ご紹介した「鞠とぶりきの独楽」と、リズムが同じであることに気づいた人はおられるだろうか。気づいた人は間違いなく、八木重吉マニアである。
「鞠」は「まり」、「独楽」は「こま」と読む。回して遊ぶ、あの玩具の「独楽(こま)」のこと。
以下「鞠とぶりきの独楽」の一節を、少しく引用してみる。
てくてくと
こどものほうへもどってゆこう
こどもがよくて
おとながわるいことは
まりをつけばよくわかる
あかんぼが
あん あん
あん あん
ないているのと
まりが
ぽく ぽく ぽく ぽくつかれているのと
火がもえてるのと
川がながれてるのと
木がはえてるのと
あんまりちがわないとおもうよ
赤字にしたのは、八木重吉が得意とする、擬態語・擬声語が使われているからだ。
「てくてく」「あんあん」「ぽくぽく」、この言葉の使い方は、八木重吉が確立した表現法と言えるだろう。
で、今回ご紹介している「みんなも呼びな」でも「あんあん」が使われ、ものの見事な効果を生み出している。
この「効果」の意味は、以下のとおり。
ふつう私たちが「神」を語る時、否応もなく、仰々しいまでに形而上学的な言い回しにってしまう。
ドストエフスキーの小説で語られる「神」を挙げるまでもないだろう。
ところが、八木重吉は「てくてく」「あんあん」「ぽくぽく」といった擬態語や擬声語のリズムによって、親しみやすく、軽いユーモアを交えて、読者を神のところに案内してしまう。
八木重吉マジックと呼ぶべきだろうか。この手法は、後にも先にも、八木重吉しか成功させていない。