Views: 136
最近、二十代の時に読んだ、日本の近代詩のことがしきりと思われてなりません。深まりゆく季節のせいなのか、それとも他に深い理由でもあるだろうか、と独り首をかしげる私です。
そんなわけで、今回は日本の抒情詩の名作をご紹介することにしましょう。
日本の抒情詩の中で、もっとも感傷的で、美しいのが、立原道造の「のちのおもひに」だと私は思っています。
さっそく、引用してみましょう。
のちのおもひに
夢はいつもかへつて行つた 山の麓のさびしい村に
水引草に風が立ち
草ひばりのうたひやまない
しづまりかへつた午さがりの林道を
うららかに青い空には陽がてり 火山は眠つてゐた
──そして私は
見て来たものを 島々を 波を 岬を 日光月光を
だれもきいてゐないと知りながら
語りつづけた……
夢は そのさきには もうゆかない
なにもかも 忘れ果てようとおもひ
忘れつくしたことさへ 忘れてしまつたときには
夢は 真冬の追憶のうちに凍るであらう
そして それは戸をあけて 寂寥のなかに
星くづにてらされた道を過ぎ去るであらう
立原道造の詩には、二十代の前半の頃、親しみました。立原道造の詩は好きだったのですが、同時に物足りなさを覚え、他の近代詩人である、中原中也や八木重吉の方に強く惹かれてゆきました。
立原の詩には、高村光太郎や宮沢賢治の詩にあるような「求道性」はありませんね。八木重吉のように「祈る」詩人でもなかったし、中原中也のような「毒の分泌」もありはしなかった。
では、立原の詩には何があるのでしょうか?
今回読み返してみて、強烈なテーマとかがないところが、立原道造の詩の魅力だと思い当たりました。
何か、思想なり、詩学なり、人生観なりを、表白することは、立原にとっては「野暮」でしかなかったのではないでしょうか。
あらゆる「意味性」から逃れ、徹底した「透明な抒情性」を、精緻なソネット形式に定着させることにしか、立原道造は興味を覚えなかったのだと思います。
立原が愛するのは、もろく、はかなく、消えやすいものだけであり、愛さえも、強固であってはならないのです。
「ただ感傷的である」とか「綺麗なだけだ」とか、そういう指摘は通常は非難でしかありません。そこには少なからず軽蔑の念が込められているもの。
でも、まさに「意味のない感傷」や「ただ綺麗なだけの世界」に憧れ、それを、感傷や感性よりも、理知的に構築したのが、立原道造という詩人だと私は感じています。
表現された世界はこの上もなく感傷的で美しいけれども、その技巧はあくまで理知的であったのです。

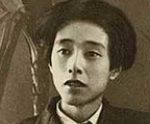

いいですねー 喜寿の爺が感銘を受けて、忍んでいます。
”のち”が無くなったよぅな、現代の絶忙のなかには、ご紹介された立原道造さんの詩を、認識感覚できる余地が、
あればこその文明だとおもいますが、文明や世界、宇宙を心に詩えるような、
感性は、感性が枯絶したかに思えるような、自分を自分だと思える(思いたいけれども、思うと、
本当の詩が書けなくなる)存在には、潤いになって、
遠からず、健康の定義にも加えられるような霊性を、
涵養する糧になっても呉れるような、
柔く弱く勁ゐ淡さが、あるからこその普遍性とゆうよりも、
通底性や、ほんとうにいまそこにあることへの延展性、
(自分が自分だけのじぶんでない何かであって、
果たすことのできないことに踏み歩みこんでみるなら生命観だけの、
存在性では語れない、、、、、
て、ここまで長々タイピングしてまいましたが、
道造さんの
、先ず、本当に読み抜いてから
はなせ、て感じのまなざし感じるので、
朗読よかったです、
やけど、
とか云えんぐらいなとこもあるりますが、
なんかこれ、出逢いの不可思議ゃなぁてとこ、
あって、
特に、最後の、コリドーてとこで、
なんに依拠してそのことばつかわれたんやろか、
て、すごく夢想してまいます、
芥川龍之介ㇳかも、
’んか、使ってはったりしましたよね、て、
思ったり、リトアニアのバルタス監督にも近いていうより、
それそのものの直球な題の映画が、ありましたが、
やっぱり、風物(諷翳と詩意象徴ゆかれ(ゆかり)のひかりのかたどり)は、
どの土地にも星にも通じるところがありながら、
悲しみが心に非ざるものごとやて文字にされん(される)のは、
存在圏非存在圏にかかわらず、
生きたるんやて思いが、
音を声にするからなんやろかなて
思たdecu(できゅ、.。
、です!
ご拝読戴いて、ありがとうございや(yay!)した!!!!