カテゴリー:立原道造

2026/01/13
重力からの解放と二つの透明感――立原道造と風花未来における「視座」と「救済」の比較論序論:時を超えた「風」の共鳴昭和モダニズムを代表する夭折の詩人・立原道造(1 ...
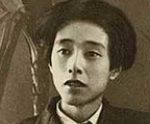
2026/01/13
昭和モダニズムを代表する夭折の詩人・立原道造と、現代のインターネット黎明期から言葉を紡ぎ続け、多くの人々に癒しを届けてきた風花未来。この二人の組み合わせは、非常 ...
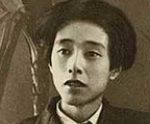
2022/02/18
立原道造の「草に寝て……」という詩をご紹介します。草に寝て……六月の或る日曜日にそれは花にへりどられた高原の林のなかの草地であつた小鳥らのたのしい唄をくりかへす ...
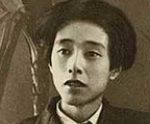
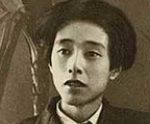
2021/12/11
立原道造の「夢みたものは……」という詩をご紹介します。夢みたものは・・・・夢みたものはひとつの幸福ねがったものはひとつの愛山なみのあちらにもしずかな村がある明る ...
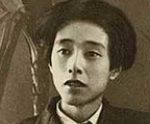
2021/12/11
立原道造の詩「眠りの誘い」という詩をご紹介します。眠りの誘(いざな)ひおやすみやさしい顔した娘たちおやすみやはらかな黒い髪を編んでおまへらの枕もとに胡桃色(くる ...
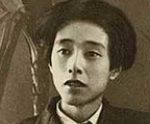
2019/02/13
立原道造(たちはらみちぞう)の「はじめてのものに」という詩を読み返して、今日は半日、この詩のことだけを考えておりました。特に「ささやかな地異はそのかたみに灰を降 ...
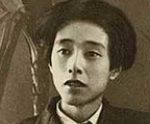
2014/10/30
最近、二十代の時に読んだ、日本の近代詩のことがしきりと思われてなりません。深まりゆく季節のせいなのか、それとも他に深い理由でもあるだろうか、と独り首をかしげる私 ...