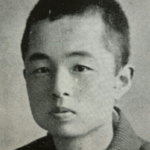Views: 9
吉野弘の「I was born」という詩をご紹介。
I was born
確か 英語を習い始めて間もない頃だ。
或る夏の宵。父と一緒に寺の境内を歩いてゆくと 青い夕靄の奥から浮き出るように、白い女がこちらへやってくる。物憂げに ゆっくりと。
女は身重らしかった。父に気兼ねしながらも僕は女の腹から目を離さなかった。頭を下にした胎児の 柔軟なうごめきを腹のあたりに連想し それがやがて 世に生まれ出ることの不思議に打たれていた。
女はゆき過ぎた。
少年の思いは飛躍しやすい。その時 僕は<生まれる>ということが まさしく<受身>である訳を ふと 諒解した。僕は興奮して父に話しかけた
ーーやっぱり I was born なんだねーー
父は怪訝けげんそうに僕の顔をのぞきこんだ。僕は繰り返した。
ーーI was born さ。受身形だよ。正しく言うと人間は生まれさせられるんだ。自分の意思ではないんだねーー
その時 どんな驚きで 父は息子の言葉を聞いたか。僕の表情が単に無邪気として父の眼にうつり得たか。それを察するには 僕はまだ余りに幼かった。僕にとってはこの事は文法上の単純な発見に過ぎなかったのだから。父は無言で暫く歩いた後、思いがけない話をした。
ーー蜉蝣(かげろう)と言う虫はね。生まれてから二、三日で死ぬんだそうだが それなら一体 何の為に世の中へ出てくるのかと そんな事がひどく気になった頃があってねーー
僕は父を見た。父は続けた。
ーー友人にその話をしたら 或日、これが蜉蝣の雌だといって拡大鏡で見せてくれた。説明によると 口はまったく退化していて食物を摂とるに適しない。胃の腑(ふ)を開いても 入っているのは空気ばかり。見ると、その通りなんだ。ところが 卵だけは腹の中にぎっしり充満していて ほっそりとした胸の方にまで及んでいる。それはまるで 目まぐるしく繰り返される生き死にの悲しみが 咽喉(のど)もとまで こみあげてるように見えるのだ。つめたい 光の粒々だったね。私が友人の方を振り向いて <卵>というと 彼も肯いて答えた。<せつなげだね>。そんなことがあってから間もなくのことだったんだよ、お母さんがお前を生み落としてすぐに死なれたのはーー。
父の話のそれからあとは もう覚えていない。ただひとつの痛みのように切なく 僕の脳裡に灼きついたものがあった。
ーーほっそりとした母の 胸の方まで 息苦しくふさいでいた白い僕の肉体ーー。
ふだんから中原中也の詩を絶賛している一人の大学生が、吉野弘の詩を読んで馬鹿にしたように言った。
「これで詩と言えるのか? やたらと長いだけで、特別深い洞察な哲学があるわけでもない。こういう文章を優れた詩として評価している現代詩とやらのレベルを疑う」
かなり高慢ちきな意見だと思われるが、実はその傲慢な大学生は私自身だった。
だが、あれから何十年も経った今、じっくりと読み返してみて、吉野弘の詩に対する私の評価は激変してしまった。
「こういう詩が好きな人、高く評価する人は少なくないだろう。ならば、現代詩の一つの現象というか、風景として、語り継ぎたい人は語り継げば良いのではないか」
詩が素晴らしいとか、そうではない、などと言っているほどの余裕はない。
ほとんどの人が詩を読まなくなっており、森羅万象を鋭敏に感じ取れる人も極めて少ないし、物事を深く考える人は激減していて、深く考えることを良いことだと思っている人も数えるほどしかいない……という嘆かわしい状況が現代なのである。
であるならば、吉野弘の詩は、確かに長い詩、散文的だし、とてつもなく深いことを伝えているわけでもないが、あわただしい日常の中において、ふと立ち止まり、心を澄まして、沈思黙考できる、そうした貴重な機会を与えてくれるのだから、多くの人に読んでほしいと推奨すべきだろう。