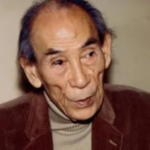Views: 3
遠い遠い、幼い頃の記憶です。
夢なのか、うつつなのか、あまりにも遠い過去のことで、わからないのですが、ただハッキリしているのは、あれほど鮮明な映像は見たことがないことです。
真昼の星群
あの晴天の午後
暗い部屋の小さな窓から
幼いわたしはひとり
真っ青な空に
無数の星を見た
いつもいっしょに
小さな窓から外を眺める
兄はその日はいなかった
真昼に星を見たのは
初めてだった
鋭い叫び声が聞こえたが
それはわたし自身の声にならない叫びだった
声にならない叫びを
小さな胸の奥に飲みこんだまま
わたしはその日
うれしいような
こわいような
そんな気持ちで
ふるえながらすごした
晴天の午後に見た星のことは
誰にも言わなかった
その日のことを
何十年も経った
今おもいだすと
ほんとうに真昼の星群を見たのか
それとも夢だったのか
わからなくなる時がある
あの時のわたしは
狂っていたのか
それとも正気すぎて
冴えかえった心の眼に
蒼穹の星が映ったのか
ただ忘れようもないのが
あの無数の星ぼしの
こわいほどの
鮮やかさ
うつくしさ
あの確かさは
たとえ夢だとしても
あれほど
はげしく
狂おしい
光景は見たことがない
とおいとおい
幼い日の記憶である
東向きに小さな窓がある、暗い部屋の記憶。
よく晴れた日には、その窓から、遠くに富士山が見えたものでした。
青空に、突然現れた星群、それらを見た、あの時の感覚が、確かに今、はっきりと蘇えりました。
あの記憶が、夢であろうと、現実であろうと、もうどうでもいい気がしています。
確かに、わたしが真昼の星群れを見た、そのことには間違いはないのですから。