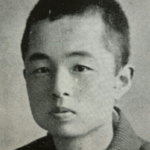Views: 74
尾崎放哉の俳句を、私は若い頃、警戒心を抱きつつ、興味を惹かれていた。
それは、石川啄木の短歌にも共通していたかもしれない。
要するに、その悲しき抒情に溺れそうになる自分が怖いのである。
尾崎放哉には、石川啄木にある、みずみずしい感傷もないので、余計に始末が悪いと毛嫌いしていたのか、尾崎放哉の俳句集を持っていいないのだ。
しかし、青春というものが遠く感じられるようになると、尾崎放哉の無防備過ぎる自虐癖に、郷愁を覚えてきている自分が悲しい……
以下、尾崎放哉の代表的な俳句をご紹介しよう。
尾崎放哉の代表的な俳句
大空のました帽子かぶらず
尾崎放哉には珍しい、ポジティブな作品である。自然讃歌、人生肯定などは、シャイ過ぎる放哉には似合わない。それだけに、「大空のました帽子かぶらず」と発句されてしまうと、感動せざるを得ない。
こんなよい月を一人で見て寝る
放哉の孤独感は半端ない。だから当然のように「一人」という言葉を、普通に使う。「こんなによい月」の明るさが、いっそう放哉の孤独を際立たせている。
咳をしても一人
「一人」という放哉節には欠かせないワードが、想いかけず「咳」という言葉につなげられてしまうと、もう見もふたもなく、放哉節に浸ってしまうしかない。
今日一日の終りの鐘をききつつあるく
哀しかろうが、寂しかろうが、この句のように、しみじみとした情緒に浸れる静かな時間を現代人は持てない。それだけでも、この句は良いのである。しんみりとした時までをも人から奪ってしまったのも、現代文明の罪だといえるだろう。
貧乏して植木鉢並べて居る
キターーーー! これぞ放哉ワールド。貧乏という傷に塩をこすりつけて、微苦笑するという悪癖である。貧乏にかぎらず、日本の詩人にはこの手の自虐癖に陶酔するタイプが少なくない。萩原朔太郎や中原中也がそれである。放哉には朔太郎や中也にある、文学の香気が薄いから、自嘲癖が露骨となる。
底がぬけた柄杓で水を呑まうとした
あ、この手の道化は、太宰治の世界に通じる。中原中也の道化より、センスがいいのではないだろうか。
犬よちぎれるほど尾をふつてくれる
う~ん、犬まで出されてしまうと、寂しさは極まってしまうではないですかぁ~。
よい処へ乞食が来た
見栄をはって人並みに格好をつけようなんて気を起こしそうになっていたところに、乞食が現れて、ああ、やっぱり、自分には乞食の方が似合っていると思い直せた、という意味に解釈している私自身は、異常だろうか。
尾崎放哉のプロフィール
尾崎 放哉(おざき ほうさい)は、1885年〈明治18年〉1月20日に生まれ、1926年〈大正15年〉4月7日)に死去した、日本の俳人。『層雲』の荻原井泉水に師事。種田山頭火らと並び、自由律俳句のもっとも著名な俳人の一人である。
東京帝国大学法学部を卒業後、東洋生命保険(現・朝日生命保険)に就職し、大阪支店次長を務めるなど出世コースを進み、豪奢な生活を送っていたエリートでありながら、突然それまでの生活を捨て、無所有を信条とする一燈園に住まい、俳句三昧の生活に入る。
その後、寺男で糊口(ここう)をしのぎながら、最後は小豆島の庵寺で極貧のなか、ただひたすら自然と一体となる安住の日を待ちながら俳句を作る人生を送った。癖のある性格から周囲とのトラブルも多く、その気ままな暮らしぶりから「今一休」と称された。