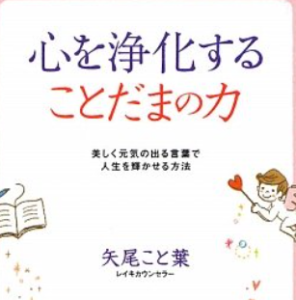- 投稿 2017/02/22更新 2019/05/25
- 言葉の力で暮らしを変える - 言葉による引き寄せ
「引き寄せの法則」に関連する本(引き寄せ本)を、あなたは何冊読んだことがあるでしょうか。
まだ「引き寄せの法則」の本を一冊も読んだことがなく、どれから読もうかと悩んでいる人にアドバイスしたいので、今回の記事を書くことにしました。
私は引き寄せの法則の専門家ではありませんが、心理学・哲学・文学を自分なりに探求してきた者として、直感的に「引き寄せ本は、読む順番、読み方を間違えると、呆気なく挫折してしまう危険がある」と思ったので、このテーマで書こうと決めました。
結論から申しますと、最初に「引き寄せの法則 ムエイブラハムとの対話(エスター・ヒックス、ジェリー・ヒックス)」を読み、次に「引き寄せの法則(マイケル・J・ロオジェ)」を読んだ方が良いと思います。
その理由を以下で、ご説明しましょう。
ヒックス夫妻の「エイブラハムとの対話」は少し難しいかもしれません。スピリチュアルな視点から書かれているからです。
わからないところは飛ばしながらでも良いですから、最後まで読んでください。万が一、途中で挫折しても諦めないで、次にマイケル・J・ロオジェの「引き寄せの法則」を読んでください。こちらは実践の手引きとなっていますので、わかりやすいでしょう。
マイケルの本も、ヒックス夫妻の本を読んでいるからこそ理解できるので、この2冊を交互に、また同時進行で繰り返し読むと、無理なく理解を深めてゆけます。
ヒックス夫妻はスピリチュアルな視点から本格的に引き寄せの法則を語り、マイケル・J・ロオジェは、NLPの公認プラクティショナーらしく実践的な解説をしてくれているのに加え、石田裕之が監修しているので、さらにわかりやすくなっているのです。
なぜ、この2冊をオススメするかと申しますと、この2冊には矛盾が少ないので、頭の中が混乱しないからです。
実際に、マイケル・J・ロオジェは、エスター・ヒックスとジェリー・ヒックスを尊敬し、夫妻の著作から大きな影響を受けています。
中には、この2冊は翻訳本なので、日本人が書いた、マンガ版を含めた、さらにわかりやすい入門書が欲しいとおっしゃる方もおられるでしょう。
しかし、それはオススメしません。まずは、上記の2冊を交互に読んで「引き寄せの法則」の基礎を学んでいただきたいと切に願います。
その理由は、それでは出版社の「思う壺」でからです。
そもそも「引き寄せの法則」を活用する方法は、簡単ではありません。法則は単純ですが、それを有効的に働かせるためには、それこそ知恵や精進や学習や体験などを合わせた「トータルパワー(総合力)」が求められます。
難しいことを無理やりわかりやすくしようとして、あたかも簡単であるかのようにアピールして、本をたくさん売ろうと、出版社はやっきになっているのです。その戦略に載せられてはいけません(苦笑)。
読書は本来「難しい、わからない」と悪戦苦闘することに醍醐味があります。そうすることで「自分で考える習慣」が養われるのです。
この「自分で考える習慣」こそが、人生の宝物だということを忘れてほしくありません。