ふだんは滅多にアニメは見ないのですが、先日、なぜか見落としていた「天空の城ラピュタ」を鑑賞しました。その感想を、ある美大生と話したところ、ぜひとも「塔の上のラプンツェル」を見るべきだと教えらえたので、今回鑑賞した次第です。
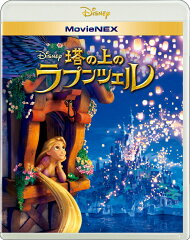
グリム動画を長編アニメ化した、2010年のディズニー作品。
結論から言いますと、傑作だと感じました。
最近、映画でも、小説でも、音楽でも、その作品が優れているかどうか、自分にとって必要か不必要かどうか、その基準がハッキリしてきたのです。
読んだ時、見た時、聞いた時、こちらにどれだけの風圧が迫ってくるか、どれほどの光に自分が照らし出されるか、どれくらいのオーラが立ち上がってくるか、それだけで私は傑作か否かを判断するようになっています。
要するに、自分の奥底に潜んでいる原初的なパワーを、呼び覚ましてくれるかどうかが、作品としての分かれ道なのです。それを「命の喚起力」と呼びたいのですが……。
ガブリエル・ガルシア=マルケスの小説を最初に読んだ時、あふれてくる光の強度、吹き上がってくる風圧の凄さにのけぞりました。その時と同質の純度の高さを感じました。
それゆえ、この「塔の上のラプンツェル」をを傑作と呼びたい、それが今の正直な気持ちです。
人は心の中に広大な空間(夢宇宙)を持って生きていることを、思い出させてくれました。その世界は、生きる歓びの根源と呼びたい光の国です。
光は生命エネルギーの源泉であり、人間も他の生命体と同じく、光を体内に取り入れ、それを生きる力に変えている、そんなことを再確認してくれる作品でした。
絵がやたらと立体的になっていることに、最初は少し違和感を覚えましたが、終いの方では、すっかり馴染んでいました。
こういう純粋な作品に接すると、現実生活はいかに夾雑物だらけであること、余計な情報にあふれすぎていることに気づきます。
余分なものをすべて捨て去り、光と風の国に旅立ちたい、そう心底感じられただけでも、大きな救いでした。なぜ救いなのかと言いますと、光と風の国は、自分の心の中に生きていることを確認できたからです。