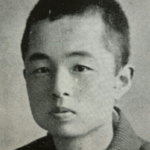Views: 88
茨木のり子の「六月」という詩をご紹介します。
六月
どこかに美しい村はないか
一日の仕事の終りには一杯の黒麦酒(くろビール)
鍬(くわ)を立てかけ 籠(かご)を置き
男も女も大きなジョッキをかたむける
どこかに美しい街はないか
食べられる実をつけた街路樹が
どこまでも続き すみれいろした夕暮は
若者のやさしいさざめきで満ち満ちる
どこかに美しい人と人との力はないか
同じ時代をともに生きる
したしさとおかしさとそうして怒りが
鋭い力となって たちあらわれる
なぜ、六月、なのか?
この詩「六月」のテーマは、まぎれもなく「希望」である。
絶望的な現状から、希望を見出そうと、力強く呼びかける、前向きな詩だ。
しかし、なぜ茨木のり子は、この詩に「六月」というタイトルをつけたのか?
おそらくは、こうだ。
「絶望」を指すのは「六月」の暗く垂れこめた雲であり、いつやむとも知れない長雨である。
「希望」を指すのは、「六月」の暗い空の向こう側にある、蒼い空に真っ白な雲が浮かぶ夏の空だ。
茨木のり子が立っているのは、絶望の季節である「六月」だが、そこから「希望」することはできる。
絶望的な状況にあっても、村を、街を、人を、祝福することはできる。だから「六月」を生きられるだ。
まだ見えない希望を鮮明にイメージさせるために、解放と祝祭の季節である「八月」ではなく、暗い忍従の季節である「六月」でなければならなかったのである。
(追記)茨木のり子の誕生日は、6月12日。自身の原点から、「希望」なるものを歌い上げたかったのかもしれない。
⇒「雨」を歌いながら、未来の希望を表現した名曲が「雨にぬれても」です。
1956年という時代
茨木のり子の「六月」という詩は、1956年(昭和31年)に発表された。
1964年には東京オリンピックが開催される。だが、茨木のり子の「六月」は、高度成長に向かう日本の高揚感を予見した詩では決してない。
茨木のり子は経済的な繁栄を夢見てはいないだろう。人が人らしく、自分が自分らしく生きられる、まっとうな世界を希求している。
しかし、おそらくは違う方向に日本は向かっているので、そうあってはならない、茨木のり子は半ば怒りを込めて希望している。
「明日」という日は「明るい日」と書く。1956年は「明日」を感じられた時代だったはずだ。少なくとも、2021年12月に生きる人々は、そう考えるだろう。
しかし、1956年という時代は、実は、日本人が本当の自分を見失ってゆく、闇雲に経済活動に突っ走り、迷走し、堕落し、真に尊いものを自ら手放してゆく、悪夢の始まりのような時代なのだ。
では、1956年当時の日本人は、「本当の自分」を明確に持ち「真に尊いもの」を大事にしていたかというと、そうではない。
戦後の混乱から抜け出ようとしていて、これから、本当の豊かさを見つける道を歩みだせるチャンスを有していたのだ。要するに、1956年から現在に至るまで、日本人は完全に道を誤ってしまったのである。
原点回帰の必要性。そもそも、日本人とは誰なのか?
では、現代と1956年当時との最大の違いは何か。それはエネルギーである。
1956年当時の日本人には、爆発的なエネルギー(潜在能力を含む)を持っていたが、現代の日本人には、それがないのだ。
では、今の私たちは「六月」という詩に「希望」見出せるか?
「希望」への道は一つしかない。「本当の自分」と「真に尊いもの」を見出すことだ。
その「希望」への道は、茨の道だろうか。