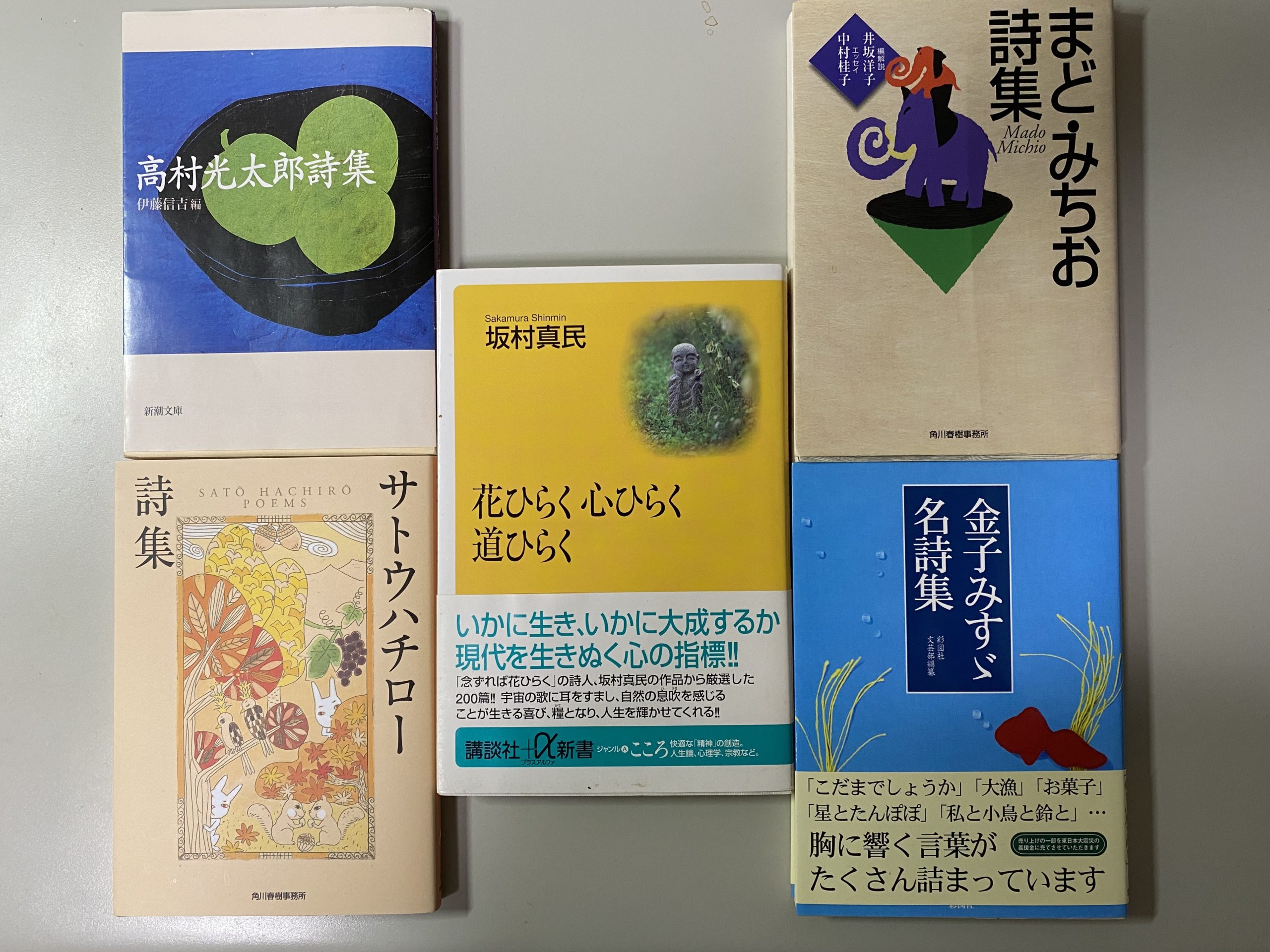今回は遠藤俊夫の「一隅を照らす」という詩をご紹介します。
さっそく、引用してみましょう。
一隅(いちぐう)を照らす
わが身を燃やして
暗きを照らす
ともしびかかげて
一隅(ひとつのすみ)を
照らしてきよめよ
われら手をとり
この世をみちびく
国宝(たから)とならん
「一隅を照らす」という言葉は、最澄が書いた『山家学生式(さんげがくしょうしき)』の中の言葉です。
この『山家学生式』は、弘仁9~10年(818~819)に順次成立。天台宗(山家)での学生養成制度を勅許されるよう願ったもの。
伝教大師が『法華経』を基調とする日本天台宗を開くに当たり、人々を幸せへ導くために「一隅を照らす国宝的人材」を養成したいという熱い想いを著述し、嵯峨天皇に提出されたとされています。
では、『山家学生式』の冒頭部分を引用いたします。
国の宝とは何物(なにもの)ぞ、
宝とは道心(どうしん)なり。
道心ある人を名づけて国宝と為(な)す。
故(ゆえ)に古人(こじん)言わく、
径寸十枚(けいすんじゅうまい)、
是(こ)れ国宝にあらず、
一隅(いちぐう)を照(てら)す、
此(こ)れ則(すなわ)ち国宝なりと。
古哲(こてつ)また云(い)わく、
能(よ)く言いて行うこと能(あた)わざるは国の師なり、
能く行いて言うこと能わざるは国の用(ゆう)なり、
能く行い能く言うは国の宝なり。
三品(さんぼん)の内(うち)、唯(ただ)言うこと能わず、
行うこと能わざるを国の賊(ぞく)と為す。
乃(すなわ)ち道心あるの仏子(ぶっし)、
西には菩薩(ぼさつ)と称し、
東には君子(くんし)と号す。
悪事(あくじ)を己(おのれ)に向(むか)え、
好事(こうじ)を他に与え、
己(おのれ)を忘れて他を利(り)するは、
慈悲(じひ)の極(きわ)みなり。
まず、以下の3行が大事。
国の宝とは何物(なにもの)ぞ、
宝とは道心(どうしん)なり。
道心ある人を名づけて国宝と為(な)す。
「道心」とは「 道徳心。仏道を修め仏果を求める心。仏道に帰依する心」のこと。
やはり何よりも「心」が大切です。「心」は目に見えませんが、実は目に見えないものこそ大切なのです。現代には視覚表現があふれかえっていますが、視覚でとらえられないものを大事にしたいもの。
「径寸十枚(けいすんじゅうまい)」という言葉の意味が難しいですよね。
以下のエピソードを知れば、理解できます。
中国の春秋時代、斉(さい)の威王(いおう)と魏(ぎ)の恵王(けいおう)が偶然狩り場で出会ったときのこと。
恵王が威王に次のように語りかけました。
「私の国は小国ですが、他国にはない立派な宝物があります。直径一寸ほどの強い光を放つ珠で、車の前後およそ十二乗分までを照らすものが十枚あります。貴国はいかがですか。大国ですので、さぞかし立派な宝をたくさんお持ちでしょう」
威王は答えました。
「私の国にはそういうものはありません。しかし優れた家来が多くおります。ある者に南城の地を守らせたところ、南隣の楚(そ)は恐れて攻め入ろうとはしません。またある者に高唐の地を守らせたところ、西隣りの趙人は東境の黄河で魚を獲ることをしなくなりました。こうした優れた家来たちが自分の持ち場で一隅を照らし、国を支えてくれています。これが私の宝です」
恵王はこれを聞いて大いに恥じ入ったといいます。
要約すれば、以下のようになるでしょう。
「直径一寸もあるような珠十枚が国宝なのではなく、世の一隅に光を与え照らす者が国宝である」
次に「一隅(いちぐう)を照(てら)す、此(こ)れ則(すなわ)ち国宝なりと」も、もう少し噛み砕かないと、教訓として生活に活かしにくいかもしれません。
「社会の片隅に生きつつ、ひたむきに自分の役割を全うすることで、社会を明るく照らすことができる人こそ、国の宝である」と素直に解釈すれば良いと思います。
この最澄の「山家学生式」の一部を、遠藤俊夫は一篇の詩にしたのです。
前半部分をもう一度、引用してみましょう。
わが身を燃やして
暗きを照らす
ともしびかかげて
一隅(ひとつのすみ)を
照らしてきよめよ
後半部分の自ら国宝となろうという意思表明も素晴らしいのですが、前半部分が特に詩作品として類まれな光を放っていますね。
ひたむきに生きることを、上記の言葉に結晶させた遠藤俊夫は、立派な修道の人であったのでしょう。