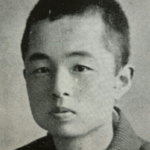Views: 4
サトウハチローの「長崎の鐘」という詩をご紹介します。
少し前に書きました「サトウハチロー「小さい秋みつけた」の言葉力」という記事のアクセスが日ごとに増えているようです。季節がまさに秋であるからでしょうか。
今回は、サトウハチローの詩を、もう一つ取り上げます。
「長崎の鐘」という曲をご存知でしょうか。これも名曲です。作曲は古関裕而(こせきゆうじ)。
長崎市に原爆が投下されたのは、 第二次世界大戦末期の1945年(昭和20年)8月9日、午前11時02分でした。
「長崎の鐘」という本を読まれた方はいるでしょうか。カトリック教徒であった医学博士・永井隆氏が書いた被爆体験記録。1949年1月に出版され、ベストセラーとなりました。
これを受けて、同じ年の1949年7月にコロンビアレコードから発売されたのが、歌謡曲「長崎の鐘」だったのです。「長崎の鐘」は松竹で映画化もされています。
この「長崎の鐘」という歌詞は、ワンコーラスめで、心奪われてしまいます。
こよなく晴れた 青空を
悲しと思う せつなさよ
うねりの波の 人の世に
はかなく生きる 野の花よ
どうして、こういう歌詞、詩が書けるのか。また、長い年月を越えて、激しく打ち寄せてくるものが感じられるのは、なぜなのか。
永井博士の辞世の句「光りつつ 秋空高く 消えにけり」を読んで、サトウハチローは、この歌い出しの歌詞をイメージしたのかもしれません。
いや、そういうことは、おそらくは問題ではなくて、究極の試練を受けた人々が、再び希望を抱いて歩き出す時、どれくらい「歌」が、「言葉」が、励ましとなり、勇気となったか、それを想像してみることに意味があると思うのです。
苦悩の質と量の違いはあるにせよ、難しい時代であることは当時も今も、変わりはないでしょう。しかし、今が当時と決定的に違うは、励ましとなる歌、勇気を与えてくれる言葉が、ラジオのスイッチを入れても聞こえてこないことです。
「リンゴの唄」や「長崎の鐘」について、語り継いでくれる人さえ、いなくなってしまいそうなのです。
戦後日本の不幸は、それは一つの運命なので仕方がないのですが、詩文学の衰弱にあったと思うのです。明治から戦前まで、日本の詩文学は隆盛を示しました。
戦後の現代詩は多くの人々を魅了する力は持ちえず、言葉の旺盛な生命力は、文字文化としての詩ではなく、楽曲として歌われる詩の方に引き継がれたと言えるのではないでしょうか。
サトウハチロウーの詩集を読むと言葉の健やかな力に驚かされます。