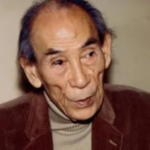Views: 0
古い自分の記憶には興味がある。
古いけれども鮮やかな記憶は、忘れかけていた自分自身を取り戻すための契機になる、そんな気がしているからだ。幼少時代のことで、しばしば想い出すシーンがある。
子供のころ、よく遊んだ路地。
そこを、一人の少女が、走っている姿。
私は真横から、その少女が駆けぬけるのを、茫然と眺めているのである。
なぜか色彩はない。
モノクロームの世界である。
日差しは感じられない。
薄い灰色の空間を、手足が長い、黒髪の少女が、音もなく駆けてゆく。
陽射しの熱さは感じられないし、少女の足音も聞こえない。
それなのに、その場の空気感は、異様なほど鮮やかに伝わってくる。
あの時は、私はうっとりと何を見ていたのであろうか。
駆けっこをしている普通の少女に、私は「神」を感じていたのかもしれない。
不思議な静寂の中で、映像だけが鮮やかに流れてゆく、遠い日の記憶である。
はっきり言えることは、当時の私は、自分の気持ちを表現する言葉を持っていなかったことだ。
白くほおおけた心の空洞を、少女が神々しい光をまとって走ってゆくのが見えた。
今ならば、そのように言葉で、何とか、あの奇妙な感じについて、言い表すことができる。
言い表しがたい、秘め事めいた神的経験について、人に伝えられるのは、言葉によってでしかできないのである。
この場合、最初に言葉があるのではない。
不可思議な感覚がまずあって、その体験を知ってもらうために、言葉を探すのだ。
言葉と言葉を組み合わせて、その微妙な感じを、伝えようと努めるのである。
私にとって、言葉の必要性は、そうした欲求から生まれているのかもしれない。
「記憶」といえば、もう一つ、忘れられない鮮明な映像がある⇒渡り鳥の記憶