Views: 158
中野重治はプロレタリア作家として知られていますが、私自身は詩人としての中野重治にだけしか興味を抱いたことがありません。
中野重治の詩の中で私が最も好きな作品をご紹介しましょう。さっそく、引用しますね。
機関車
彼は巨大な図体を持ち
黒い千貫の重量をもつ
彼の身体の各部は悉く測定されてあり
彼の導管と車輪と無数のねじとは隈なく磨かれてある
彼の動くとき
メートルの針は敏感に廻転し
彼の走るとき
軌道と枕木と一せいに振動する
シャワッ シャワッ という音を立てて彼のピストンの腕が動きはじめるとき
それが車輪をかきまわして行くとき
町と村々とをまつしぐらに駆けぬけて行くのを見るとき
おれの心臓はとどろき
おれの両眼は泪ぐむ
真鍮の文字板を掲げ
赤いラムプを下げ
常に煙をくぐって千人の生活を搬ぶもの
旗とシグナルとハンドルとによって
輝く軌道の上を全き統制のうちに驀進(ばくしん)するもの
その律儀者の大男の後姿に
おれら今あつい手をあげる
記憶違いでなければ、この「機関車」は、高校の教科書に載っていました。
長い歳月を経て、今日読み返したのですが、当時の純粋な感動が、鮮明によみがえりました。
今ここで特筆すべきは、この詩のオリジナリティです。
日本の近代詩人、現代詩人に限らず、この手のテーマ、モチーフは扱う人がほとんどいませんでした。
中野重治の視点が珍しいということではなく、多くの詩人はあえて避けてきた領域だったのです。
逆に言えば、中野重治は、多くの詩人が目を背けたがって来た領域に首を突っ込み、そこステージを自分の主戦場として選んだとも断定できるでしょう。
「機関車」は、中野重治の詩論に、愚直なほど忠実に歌い上げた詩であることは明白です。
ともあれ、たくましい人間の生命力、無骨で荒々しい生き様を讃美することは、日本の詩人が忘れ果てようとしているテーマだと感じました。
過剰に情報があふれる現代社会において、中野重治の目指した、強烈な皮膚感覚に飛んだ詩世界は、新鮮であり、一つの理想郷に見えてくるのではないでしょうか。
画家のミレーやゴッホの描き出した世界を詩にしてみる、そうした極めてシンプルかつ果敢な挑戦をする詩人がこの21世紀に登場してもおかしくない、となぜか思えるから不思議です。

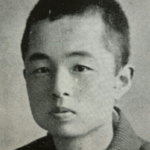

「全き統制の中に」(全き統制のうちにの間違いでした)のフレーズが頭にこびりついて30年ぶりに調べたら、中野重治の詩だったのですね。「機関車」よく覚えています。これは確か中学校の教科書じゃなかったかな?国語の先生の顔までセットで思い出しちゃいます。
このぐらいの年にならないと詩なんてわからないのかな?あの頃は「ふーん」って感じでしたが。
蛙って「●」こんな詩もこの人でしたっけ?^^;
この詩を8年ぶりにまた調べている自分がいました。
「全き統制の中に」って間違えて覚えて頭にこびりついているところまで同じ。
でも、今度は中野重治は覚えていました。
8年前の自分がこんなコメント書いてるなんてびっくり。
国語の先生懐かしいなぁ。
自分に敬意を込めてレスしときます^^;