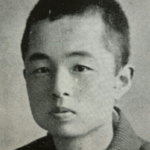Views: 11
中野重治の詩に対する姿勢をよくあらわした詩があります。それが「歌」です。
歌
お前は歌ふな
お前は赤まゝの花やとんぼの羽根を歌ふな
風のさゝやきや女の髪の毛の匂ひを歌ふな
すべてのひよわなもの
すべてのうそうそとしたもの
すべての物憂げなものを撥(はじ)き去れ
すべての風情を擯斥(ひんせき)せよ
もつぱら正直のところを
腹の足しになるところを
胸先を突き上げて来るぎりぎりのところを歌へ
たゝかれることによつて弾ねかへる歌を
恥辱の底から勇気をくみ来る歌を
それらの歌々を
咽喉(のど)をふくらまして厳しい韻律に歌ひ上げよ
それらの歌々を
行く行く人々の胸廓にたゝきこめ
「擯斥(ひんせき)」は「しりぞけること。のけものにすること。排斥」の意。
以前、中野重治の詩「機関車」を紹介したことがあります。
「機関車」は実に力強く、読み終わった後に体が熱くなるかのような充実感を覚える作品でした。
今回ご紹介した「歌」のテーマは「機関車」と同じではないかと思われます。
人間の生命エネルギーと勇気、闘う姿勢を鼓舞する。
「歌」は、まぎれもない詩ですが、同時に、中野重治独自の「詩論」だとも言えます。
明治維新から始まった日本近代詩の流れから、中野重治は大きく逸脱していることは明らかです。
良い意味でのアウトサイダーであることは間違いありませんが、プロレタリア文学として中野重治を分類することで、彼の業績を規定したくはありません。
中野重治の詩が追求したテーマは、人が人であるために、人が人らしくあるために、どうしても必要な命題である断言すべきです。
生命肯定を高らかに歌い上げる詩人は、古今東西を見渡しても、そうそういるわけではあありません。
現代文明に傷つけられながらも魂の無垢は保ち続け、原始的な命の炎を歌う詩人こそ、現代に必要なのではないでしょうか。
「機関車」と「歌」は、中野重治のメインテーマを象徴する作品。この中野重治の切り開いた道を、継承してさらに豊かな実を結ばせた詩人、真の後継者は、まだ出現していません。