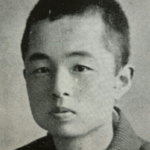Views: 209
今回ご紹介する詩は、木下夕爾(きのしたゆうじ)の「晩夏」です。昔は教科書にも載っていたらしいのですが、ご存知でしょうか。
晩夏
停車場のプラットホームに
南瓜(かぼちゃ)の蔓が匍(は)いのぼる
閉ざされた花の扉(と)のすきまから
てんとう虫が外を見ている
軽便車がきた
誰も乗らない
誰も降りない
柵(さく)のそばの黍(きび)の葉っぱに
若い切符きりがちょっと鋏(はさみ)を入れる
木下夕爾(1914年10月27日~1965年8月4日)は、日本の詩人、俳人。
第一詩集「田園の食卓」が出版されたのが1939年で、最後の詩集「笛を吹くひと」が出版されたのが1958年ですから、戦前から戦後にかけて活躍した詩人だと言えます。
近代詩と現代詩の中間に位置する、ユニークな牧歌詩人と呼ぶべきでしょうか。
さて、この「晩夏」は初めて読んだのは、私がまだ20代のはじめの頃です。
当時、愛読していた、中原中也にある「生き焦っている感じ」は、木下夕爾の詩にはありませんでした。
血気盛んな20代の私は、木下夕爾の詩で満足はできなかったのですが、束の間の和らぎを得ることができたのです。
こうした牧歌的な抒情が、これほどまでに巧みに、かつシンプルに表現された詩はほかにはなく、日本の詩の歴史にとっても、また私にとっても、今でも非常に貴重だと感じるのです。