カテゴリー:ホ・ジノ

2024/10/17
韓国映画「二つの光」は、2017年に制作された。監督は、あの名作「八月のクリスマス」で有名なホ・ジノが担当。「二つの光」はこちらで視聴できます。ホ・ジノらしい、 ...


2016/10/02
今回は韓国映画をご紹介。「八月のクリスマス」で有名なホ・ジノ監督の4作目「ハピネス」。⇒映画「ハピネス」はこちらで視聴可能ですホ・ジノ監督が追求するテーマ「死と ...
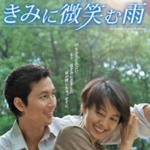
2016/09/30
前回に続き、ホ・ジノ監督作品を取り上げます。「きみに微笑む雨」今回は、ホ・ジノの精髄に、どっぷりと浸ることができました。「きみに微笑む雨」2009年11月14日 ...

2016/09/29
昨日の深夜、久しぶりに鑑賞したのが、ホ・ジノ監督の映画「八月のクリスマス」。私がこれまで観た韓国映画の中で、ベスト1にあげたいほどの傑作です。というか、これこそ ...
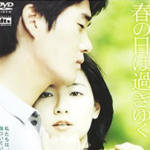
2016/09/28
私が最も敬愛する映画監督の一人、ホ・ジノの作品をご紹介しましょう。今回取り上げるのは「春の日は過ぎゆく」です。春の日は過ぎゆく2001年韓国・日・香港監督:ホ・ ...