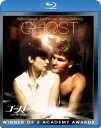- 投稿 2015/03/31更新 2018/05/26
- 日本語 - 間違えやすい日本語
「ゆうしゅうのびをかざる」を漢字で書きなさいと言われて「有終の美を飾る」と書ける、そう言い切れますか?
「優秀の美」と、うっかり書いてしまわないでしょうか。
やはり、この場合も、言葉の意味を正しく理解しておけば、間違うことはないのです。
「有終の美」を大辞泉は、以下のように説明しています。
ゆうしゅう‐の‐び【有終の美】
物事をやりとおし、最後をりっぱにしあげること。結果がりっぱであること。「―を飾る」◆ 「優秀の美」と書くのは誤り。
問題は「有終」という言葉の由来です。これについて知ると、もう間違えようがなくなります。
「有終」は、『詩経』大雅・蕩の「初め有らざるなし 克く終わり有る鮮し」から来ている言葉です。大辞林の解説を引用しましょう。
初め有らざるなし、克(よ)く終わりあるは鮮(すくな)し
〔補説〕 「詩経(大雅、蕩)」による。民は最初は善を慕う心をもっているが、善を全うする人は少ない意から
物事のし始めはみな立派であるが、その終わりを全うするものは少ない。
ですから「有終の美を飾る」とは「終わりをしっかりしめくくるということ」「最期までやりとげ、立派な成果をあげること」という意味になるのです。
「有終」が「初め有らざるなし 克く終わり有る鮮し」から来ていること、そして、それが「物事のし始めはみな立派であるが、その終わりを全うするものは少ない」という意味であることが、少し難しいですよね。
でも、一度知ったら、もう二度と間違えないと断言できそうです。