Views: 3
※この記事は、鳥居の「キリンの子 鳥居歌集」を一読した直後の印象記録に過ぎません。
鳥居と呼ばれる歌人の「キリンの子 鳥居歌集」を今日読み始めたのだが、その時から、体のそこここに痛みが出ている。
これ以上、読み続ければ、私が壊れてしまうのではないか、そう思い始めるほどの、痛みを伴う読書となっている。
体の各所に痛みが出るという読書経験は、おそらくは初めてである。
鳥居という名の魂(命)は、水色の割れた磨りガラスである。
この鳥居という少女は、真綿で包まれるような優しさを拒絶している。鳥居は抱かれることも抱きしめることもできず、呆然と立ち尽くしている。
慈しみという名の感情を抱いても、彼女は素直に対象を抱きしめられないほど、傷んでいるのだ。
痛みが激し過ぎて、無感覚になった経験のある者だけがわかる、極限における不感症状態がこの歌集には満ちている。
生身の自分から距離をおいて、見たり感じたりすることは、作家ならば誰もがやっていることだ。しかし、鳥居は、日常という時間の中で呼吸している自分から乖離して自分自身をとらえることに、慣れすぎている。
鳥居は、蒼白い色をした磨りガラスである。その磨りガラスは無惨に割れており、その鋭い割れ口は、鋭いがゆえに美しい。
鋭利な割れ口は、優しく包まれることを拒否しているかのようだ。
いや、拒否しているのではなく、優しく抱かれたとしても、体重をその温かい手にゆだねられないほど、傷つきすぎている。
例えば、私が鳥居の頬に残る涙のあとを、指でこすってから、そっと抱き寄せても、彼女は拒みはすまい。
だが、決して、自ら私にもたれかかりはしないだろう。
「キリンの子 鳥居歌集」を読む辛さは、そして同時に、この歌集の稀有な美しさは、その割れたままの水色摺りガラスの放心にある。
暗い湖で溺れた後の冷えた体に、体温は戻りつつあることは確かだ。
割れたガラスは、長い時間を経て、いつか、球体に姿変えるだろうか。手の温もりに自ら応じる生命体となるであろうか。
以下、鳥居調とも呼ぶべき代表的な短歌を引用しておこう。
これからも生きる予定のある人が三か月後の定期券買う
次々と友達狂う 給食の煮物おいしいDVシェルター
泣き叫び連れ出されていく入居者を「またか」と思う 慣れたふりして
誰も知らないおとぎばなしを聴いている水子地蔵が寄り集まって
音もなく涙を流す我がいて授業は進む次は25ページ
私でない人が座る教室の私の席に私はいない
白々となにもかなしくない朝に鈍い光で並ぶ包丁
目覚めれば無数の髪が床を埋め銀のハサミが傍らにある
少年はブランコ揺らす拳銃の錆びた匂いに掴まりながら
銃声は空にひびきて戦死者の数だけさくらさくら散り初む
鳥居の「キリンの子 鳥居歌集」に、癒しはあるのか。
鳥居の「キリンの子 鳥居歌集」を読みながら、今さらながらに「詩とは何か」というふうなことを想っていた。
考えていたわけではない。自然と頭に詩のことが浮かんでくるので、「想う」という言葉がふさわしいだろう。
鳥居の歌集を読むのが辛く感じるのは、歌っている歌人の魂が今もなお癒されていないからだ。
傷口が柘榴(ざくろ)のように割れたままで、その痛みは苛烈な速度で読む者に伝染する。
前回の感想文で「鳥居は、鋭く割れたままの蒼白い摺りガラス」だと私に書かせたのは、鳥居の受けた傷の深さと大きさであろう。
正直、鳥居が今もなお抱く苛烈な痛みのオーラを、まともに被爆したら、読む方が壊れかねない。
初めてこの鳥居の短歌を読み進めた時、私の体のあちこちに痛みが生じたのは、その強すぎる負の電磁波のためである。
しかし、鳥居が発するオーラの受け取り方を、読む側がコントロールできるようになると、鳥居の短歌は「負の歌」と「正の歌」があることが見えてくる。
私、風花未来としては、鳥居の「負の歌」を「柘榴(ざくろ)歌」と、そして「正の歌」を「蜜柑(みかん)歌」と呼びたい。
説明するまでもないが、「柘榴の歌」は、傷口がパックリと割れたままの痛みの歌(痛みさえ感じない無感覚の歌も含む)を指す。
「蜜柑の歌」は、ほんの微かであっても「温もり」が感じられる歌、つかのまであっても「安らぎ」が得られる歌を指す。
鳥居の柘榴系の歌に過剰反応すると、この歌集は読み進めない。だから、鳥居の歌集を愛読するためには、読書の特殊なテクニックが必要となる。
冷静に分析すると、柘榴が並んでいる中に、時おり蜜柑が差し込まれているのが、「キリンの子 鳥居歌集」の基本構成であることに気づく。
だから、今回の記事タイトルにある「鳥居の短歌には、癒しはあるのか」という問いの答えは、「ある」である。
「ある」という意味をもう少し詳しく語る意味はあると思う。
柘榴の歌が圧倒的に多いが、蜜柑の歌も挿し込まれているので、癒されるというのでは不充分だ。
鳥居の歌の「癒し」の本質は、鳥居という生命体の健全性にある。鳥居は死んでいない、生きている。言葉にはしていないが、明らかに、鳥居は前向きに生きようとしている。体温はまだ低いが、温もりはあるのである。
その生命の自然な鼓動が感じられれば、「キリンの子 鳥居歌集」に癒されることは可能なのだ。
以下で、鳥居の「蜜柑の歌」だけを、引用してみたい。
公園の樹や噴水や向日葵が届かざる空の高さを測る
ビル街に雪は降りだしひとびとの歩みの速度一瞬ゆるむ
夢で見たどこかの街に少し似てそのマンホールは海へつながる
ふいに雨止むとき傘は軽やかな風とわたしの容れものとなる
手を繋ぎ二人入った日の傘を母は私に残してくれた
目を伏せて空へのびゆくキリンの子 月の光はかあさんの色
大きく手を振れば大きく振り返す母が見えなくなる曲がり角
傘の穴洩れて零れる雨粒が今ゆっくりと頬つたいおり
空色のペン一本で描けるだけの空を描いてみたい昼すぎ
※以上の感想は、鳥居氏の歌集を一読し、その鮮烈な印象が消えないうちに言葉に定着したいと思って、短時間で書き上げたものです。鳥居氏の歌集に関する、私なりの(正規の)評価は別の機会に書いてみたいと思っております。

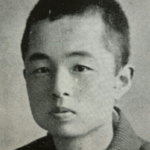

(・∀・)イイネ!!