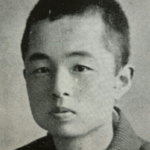Views: 4
坪野哲久(つぼのてっきゅう)の短歌をご紹介しよう。
母よ母よ息ふとぶととはきたまへ
夜天は炎えて雪ふらすなり
この歌は、昭和13年、坪野哲久が母親が危篤という報せを受けて、10年ぶりに故郷である能登に帰った時のものである。
本人であれ、他者であれ、生死の境に臨場した時に、名作詩はしばしば生まれている。
愛する者の死に接した時は、なおさらである。
斎藤茂吉の「みちのくの母のいのちを一目見ん一目見んとぞただにいそげる」は、あまりにも有名である。
今回ご紹介した「母よ母よ息ふとぶととはきたまへ夜天は炎えて雪ふらすなり」には、二つの強烈な表現がある。
息ふとぶととはきたまへ
息を吸うのではなく、吐くという点に注目。
気功を習っていた時、呼吸法の大事さを知ったのだが、特に「息を吐く」こと、吐き方に、気功の極意があるのではないかと何度となく思ったものだった。
「息ふとぶととはきたまへ」とは「生きよ」という強い願いであるとともに「豊かに、しみじみと生を実感してください」という祈りだったのではないか。
夜天は炎えて雪ふらすなり
人間は死の間際、天と交信すると私は信じている。
真昼の晴天に昇天する命もあるが、暗く重い夜の空が、うごめき、のたうちまわって炎を燃やし、雪を降らせることもあるだろう。
真昼の昇天を描いたのは、あのガルシア=マルケスの「百年の孤独」だった。
逆に、荒れた雪の空と交信しながら死んで行った妹を歌ったのが、宮沢賢治の「永訣の朝」であり、坪野哲久のこの短歌である。