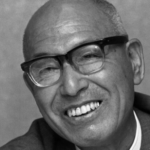
2019/04/17
中野好夫(なかのよしお)の「文学の常識」という著書をご存知でしょうか。中野好夫という名前を知らない人が多いのではないかと思います。「文学の常識」は文庫本ですが、 ...
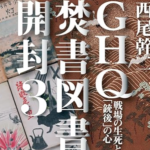
2017/01/02
本 - エッセイ・評論 - 美しい日本語の作品 - 歴史
もちろん、日本の歴史を見直すために、西尾幹二氏の「GHQ焚書図書開封」を読んでいます。またそれと同時に、私自身の、そして日本人の「心のふるさと」を見つけるために ...
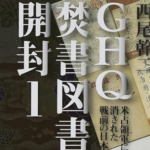
2016/12/30
来年、2017年の私のテーマは「心のふるさとを探す旅」を続けることに決定しました。ふるさとという言葉にはいろんな意味があります。生まれ故郷という意味をありますが ...
- No Image
2015/08/13
いまや流行語のようにさえなってしまっている「集団的自衛権」ですが、この言葉は実にわかりにくいのですね。このわかりにくい「集団的自衛権」という言葉を、わかりやすく ...
- No Image
2012/08/19
齋藤孝の「理想の国語教科書」という本を今日、喫茶店で読んでいました。どういう本かと言いますと、31の名文を選んだ本です。古今東西の選りすぐられた文章ばかりですか ...
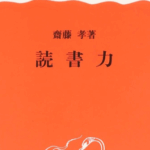
2012/01/13
昨日は病院の定期検診がありました。あまり流行っていない病院なので待たされることは少ないのですが、昨日は珍しく待ち時間が長かったのです。その時に読んでいたのが、齋 ...
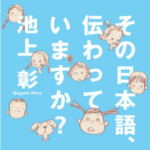
2011/12/04
本 - エッセイ・評論 - 文章の書き方 - 文章の書き方講座 - 文章の書き方
当ブログのテーマは「言葉」です。そのため、ほとんど毎日、日本語に関する本を読むことになります。というか、「言葉」「日本語」「文章」などについて、何かしら書いてい ...
カテゴリー:エッセイ・評論