
2024/07/17
先日、お配りした「検索エンジンに好かれるコンテンツの作り方」、いかがでしたでしょうか?このレポートの最後の項目で、「リライトは基本的にやってはいけない」と述べま ...

2024/07/17
ブログやメルマガなど、自分メディアで情報を配信する時、注意しなければいけないことに「著作権」があります。他のサイトのコピペ、雑誌や新聞記事の転用などは、著作権侵 ...

2021/11/25
今日は、読者の方からのご質問にお答えしながら、風花スタイルの本質について、お伝えできればと思っています。●風花スタイルに関心を寄せてくださる人たちの傾向ネットビ ...

2020/07/31
ドラマチック文章術という言葉を耳にしますと、初心者の方は、難しそうに感じるかもしれません。心配しないでください、大事なのは、最初に本質(核心)を理解することです ...

2020/06/07
●リライトは著作権違反です。リライトを外部スタッフに依頼してはいけません。なぜなら、リライト記事は著作権違反であり、グーグルが現在、厳重に精査し、検索エンジンか ...
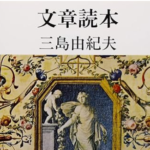
2019/07/02
当ブログ「美しい言葉」の一部をYouTubeの「風花未来チャンネル」で語っています。そのため、最近、YouTubeを見る機会が多いのです。昨日見て、感心してしま ...
- No Image
2019/06/28
太宰治の「走れメロス」を久しぶりに読みました。学生時代に最初読んで、その後も何度か読み返しているのですが、それにしても、10年以上は読んでいませんでした。古い本 ...
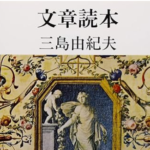
2019/06/06
ブログやメルマガなど、自分メディアで情報を配信する時、注意しなければいけないことに「著作権」があります。他のサイトのコピペ、雑誌や新聞記事の転用などは、著作権侵 ...
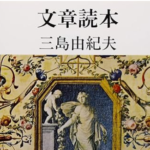
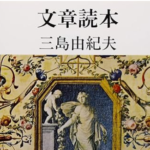
2019/05/28
最近、いろんなブロガーさんの文章を読んでいて、強く感じ入ったことがありましたので、それについて書いてみたいと思います。読者に共感されにくい文章の特徴この書き方だ ...
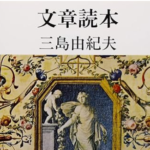
2019/05/27
読んだ本について書く場合、いろんなスタンスがあります。「感想」「書評」「ブックレビュー」、この3つの書き方は、それぞれ違うのです。【感想】「感想」は、自分が読ん ...
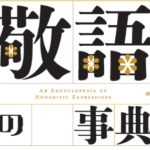
2018/05/29
日本語 - 敬語の正しい使い方 - 文章の書き方 - 文章力アップに役立つ本まとめ
敬語の苦手な人は多いですよね。私も苦手でした。私が実際に使ってみて、非常に役立った「敬語の使い方がわかるようになる本」を、厳選してご紹介します。■出口汪の「好か ...
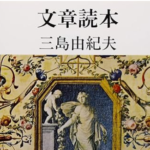
2018/03/08
これまで文章の基本ルールについて、シリーズでお伝えしてきました。今回は、それらの記事をまとめてみましたので、ご活用ください。 「体言止め」の長所と短所をまとめま ...
- No Image
2018/01/26
風花塾の塾生さんに、「文章力の基本」を養っていただくためには、どんなテキストを作成したらよいか、かなり悩みました。そのために、現在、私の前には、30冊ほどの文章 ...
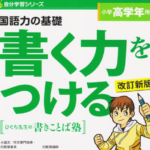
2018/01/25
インターネットを活用して収益を上げるのがネットビジネス。ネットビジネスの様々なシーンで求められるのが、文章力です。文章力の向上こそ、ネットビジネス成功のための基 ...
- パンくずリスト
- ホーム
- ›
- 文章の書き方
カテゴリー:文章の書き方