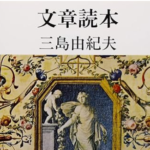
2018/03/08
これまで文章の基本ルールについて、シリーズでお伝えしてきました。今回は、それらの記事をまとめてみましたので、ご活用ください。 「体言止め」の長所と短所をまとめま ...

2017/12/12
一つの文の中に「の」を3つ以上、続けざまに使うと「この人は文章の初心者だ」というレッテルを貼られる場合があります。「の」をいくつ使っても、文法的な間違いにはなり ...
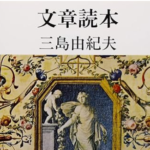
2017/12/11
わかりにくい、意味がとりにくい文の典型的なパターンの一つが主語と述語の関係がはっきりしないこと。主語と述語の関係がはっきりしない原因の多くは「主語と述語が離れす ...
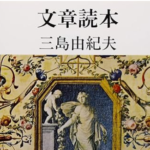
2017/11/18
文章の書き方に関する本を読みますと、例外なく「です・ます」調か、「だ・である」調のどちらかに、文体を統一しなさいと書かれています。「です・ます」調と「だ・である ...

2017/11/06
以前、「さ入れ表現」と「二重敬語」に注意という記事を書いたことがありました。間違いやすい日本語の中には、その他には「ら抜き」言葉(表現)があります。それと、「れ ...
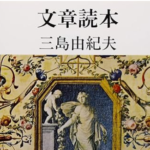
2017/04/04
体言とは名詞や代名詞などのこと。この体言で文を終えることを「体言止め」と呼びます。文章の出来不出来を、プロとアマとで比較しますと、もっとも顕著にあらわれるのが、 ...
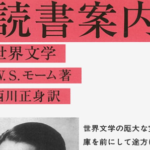
2015/04/24
文章の書き方 - 文章の基本ルール - 文章の書き方 - 文章指南書
「文章の書き方」「文章作法」「ライティング術」などの本を読みますと、必ず載っているのが「表記の統一」という項目です。例えば、以下の文章を読んでみてください。どな ...
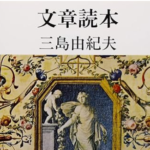
2014/12/16
このコーナーでは「文章の基本ルール」についてお伝えしています。「今さら誰も教えてくれないこと」「今さら誰にも聞けないこと」などが多く出てくることでしょう。つまり ...
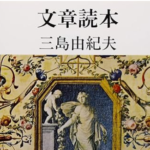
2014/12/13
カタカナ語の使い方にも注意が必要です。例えば、「コピーライター」という言葉。日本語に直すと「広告文案家」となります。この場合は、日本語の方が意味はわかりやすいで ...
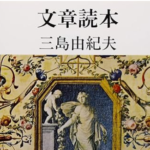
2014/12/12
初心者の文章を読むと、かなり気になるのが、接続詞が多すぎることです。「接続詞の多用をつつしむこと」は、文章作法の基本中の基本。「良い文章には接続詞は必要ない」と ...
- No Image
2014/12/11
「出れる」「見れる」「食べれる」といった、いわゆる「ら抜き表現(言葉)」は、公性を重んじる企業サイトや公式サイトなどはもちろん、やはり、個人メディアであるブログ ...
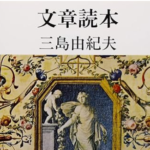
2014/10/23
以前、同じ意味の言葉は繰り返さないことを述べました。二重表現(重複表現)の禁止です。⇒二重表現(重複表現)に気をつける今回は、同じ言葉を重複して使わないことにつ ...
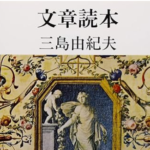
2013/10/16
文章の書き方 - 文章の基本ルール - 文章の書き方 - 文章の書き方講座 - 文章の書き方
「です・ます調」と「だ・である調」については、以前にも書いたことがあります。その記事はこれです⇒「です・ます」調と「だ・である」調の使い方比較的に表現が自由であ ...
- No Image
2013/07/16
今回の話題は文章ではなく、文のことです。文章は文の集まりでできています。ですから、文章は、いくつかの文で自分の意見などを述べたものを指すのです。一つの文が長すぎ ...
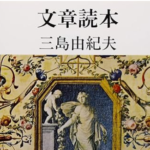
2013/07/15
文末表現が単調な文章は読みにくいので、注意してください。例えば、以下のような文章。「文章の書き方」に関する本は、これまでにかなりの冊数を読んできました。この間、 ...
カテゴリー:文章の基本ルール