- 投稿 更新
- 文章の書き方 - 文章の基本ルール
Views: 0
わかりにくい、意味がとりにくい文の典型的なパターンの一つが主語と述語の関係がはっきりしないこと。主語と述語の関係がはっきりしない原因の多くは「主語と述語が離れすぎている」ことにあるのです。
主語と述語の関係は小学3年生くらいで教えているらしい。しかし、大人でも、いきなり主語と述語について文法的に説明しなさいと言われても、すぐに理路整然と語れる人の方が少ないのではないでしょうか。
「主語」について、大辞林は以下のように解説しています。
しゅご 【主語】
(1)文の成分の一。文の中で、「何がどうする」「何がどんなだ」「何が何だ」における「何が」を示す文節をいう。「犬が走る」「空が青い」「花散る」における「犬が」「空が」「花」の類。主辞。〔日本語においては、主語は必ずしも表現される必要がなく、文に現れないことも多い〕
また、大辞林は「述語」について、以下のように説明しています。
じゅつご 【述語】
(1)文の成分の一。文中で「何がどうする」「何がどんなだ」「何が何だ」における「どうする」「どんなだ」「何だ」にあたる語または文節をいう。「花が散る」「頬(ほお)が赤い」「あれが駅だ」における「散る」「赤い」「駅だ」の類。
デジタル大辞泉、以下のように解説。
じゅつ‐ご 【述語】
1 文の成分の一。主語について、その動作・作用・性質・状態などを叙述するもの。「鳥が鳴く」「山が高い」「彼は学生だ」の「鳴く」「高い」「学生だ」の類。
さすがは辞書ですね、これなら、主語と述語について、よくわかりますね。
では、主語と述語の書き方で、悪い例をあげてみましょう。
ある映画評論家は、日本はかつて質の高い映画がたくさん作られ、映画王国であったけれども、その原動力になったのは、すぐれた映画監督が大勢いたからであって、現在の映画の衰退の原因は優秀な映画監督が少ないことが原因だから、日本の映画を復活させるためには、まずは国が政策として、映画監督を育成することに力を注ぐべきだと主張している。
非常にわかりにくくありませんか。その理由は、文が異様に長いこと。また、上の文には、主語が5つもあるからです。
そして何よりも「ある映画評論家は」という主語と呼応する述語「主張している」が、離れすぎていることが、上の文をわかりづらくしています。
では、わかりやすく書き直してましょう。
ある映画評論家は、次のように主張している。日本はかつて質の高い映画がたくさん作られ、映画王国であった。その原動力になったのは、すぐれた映画監督たちだ。現在の映画の衰退の最大の原因は、優秀な映画監督が少ないことである。したがって、日本の映画を復活させるためには、まずは国が政策として、映画監督を育成することに力を注ぐべきだと。
いかがでしょうか。かなり、意味がとりやすくなったかと思います。
主語と述語は離し過ぎず、できるかぎり近くに置くようにしましょう。
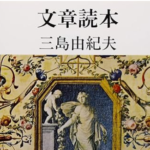

さらにシンプルにしてみました。
ー原文ー
ある映画評論家は、次のように主張している。日本はかつて質の高い映画がたくさん作られ、映画王国であった。その原動力になったのは、すぐれた映画監督たちだ。現在の映画の衰退の最大の原因は、優秀な映画監督が少ないことである。したがって、日本の映画を復活させるためには、まずは国が政策として、映画監督を育成することに力を注ぐべきだと。
ー改良文ー
ある映画評論家によると、日本はかつて映画王国であった。
すぐれた監督達により、質の高い映画がたくさん作られていた。
現在は監督が少ないために映画が衰退している。
日本の映画を再興させる為には国が映画監督の育成に力を注ぐべきだ。
ー事実文ー
かつて映画王国だった日本。その日本の映画監督が減少している。
その為に映画が衰退している。国が映画監督の育成に力を注いで欲しい。
ーつまり何を言ってるのか文ー
映画監督が減ったので増やそう。