
2023/12/14
アルベール・カミュの代表作「異邦人」を、私は二十歳の時に読んだ。あれから気が遠くなるほどの年月が流れた今、この小説のことを振り返ると、やはり……と結論づけたくな ...
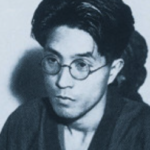
2019/12/12
良い本に限って、絶版になり、なかなか読めないことがあります。また、極めて優れた作品であってもマスコミが取り上げることがないので、忘れ去られている作品も多いのです ...
- No Image
2019/08/26
原民喜の小説「夏の花」を新潮文庫で読みました。最初にまず記しておかなければいけないのは、裏表紙の紹介文についてです。「現代日本文学史上もっとも美しい散文」とあり ...
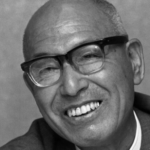
2019/04/17
中野好夫(なかのよしお)の「文学の常識」という著書をご存知でしょうか。中野好夫という名前を知らない人が多いのではないかと思います。「文学の常識」は文庫本ですが、 ...
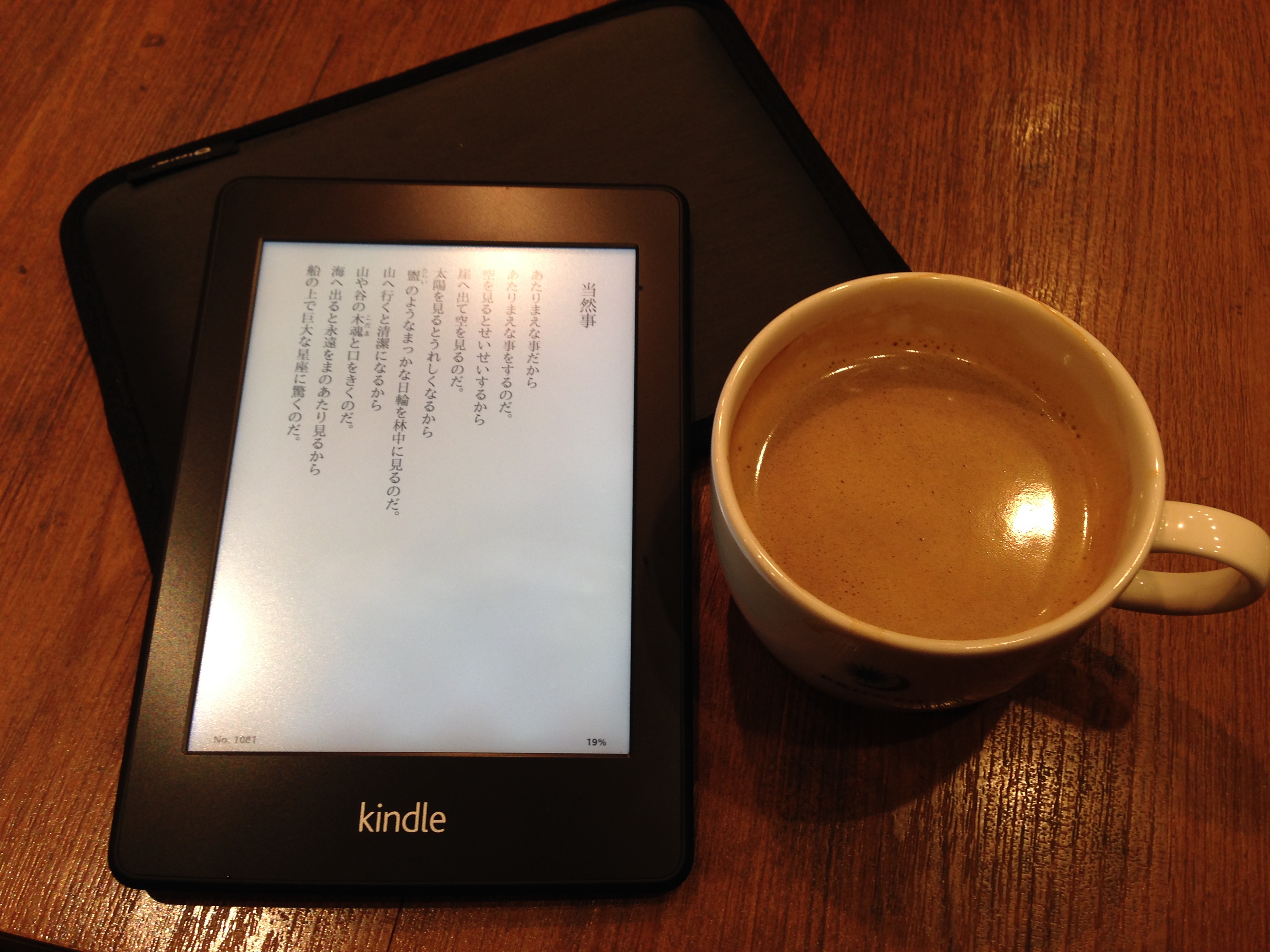
2019/04/11
紙の書籍は場所をとるので、狭い部屋に住んでいる私にとっては「本の断捨離」は、生活の知恵というより、生きるための必須要件です。本の断捨離をかなえるには、要するに、 ...
- No Image
2019/04/10
戸川幸夫の「高安犬物語(こうやすいぬものがたり)」を再読しました。思うこと多々あったのですが、突きつめると、以下の点に集約されるかと思います。1)抜きんでた筆力 ...
- No Image
2018/03/17
このブログ「美しい言葉」では、何度か戸川幸夫の小説について触れてきました。⇒「高安犬物語」の感想⇒戸川幸夫「爪王」を読んでみてください。今回取り上げる小説「熊犬 ...
- No Image
2017/09/11
今日取り上げるのは、本多孝好の小説「眠りの海」。1994年作。これほど稚拙な小説を久しぶりに読んだ気がする。腐しているのではない。逆だ。なぜこれほど未成熟な小説 ...

2017/09/10
今回取り上げる小説は、スティーヴン・キングの「デッド・ゾーン」です。映画の「デッド・ゾーン」については、以前、このブログで感想を書いたことがあります。小説「デッ ...
- No Image
2017/07/26
「シートン動物記」は映画「ハチ公物語」を見て感動したために、読み始めました。「シートン動物記」は私が読んだ最初の物語だと言っていいかもしれません。私は作文が大の ...

2017/07/13
映画「おくりびと」は以前、かなり話題になりましたよね。この映画の原点となった著書をご存知でしょうか。これがその本「納棺夫日記」です。本木雅弘がこの著書を読んで感 ...
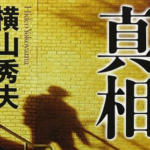
2017/05/13
横山秀夫の短編集「真相」の中に収録されている「花輪の海」を読んだ感想を書きとめておくことにします。私はエンターテインメント小説はそれほどたくさんは読んでいません ...
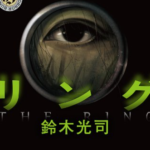
2017/03/08
以前は、エンタメ小説をたくさん読みました。その中で最も面白かった作品が、今日ご紹介する「リング」です。⇒小説「リング」はこちらで読めます1991年に発行された、 ...
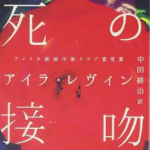
2017/02/25
今回取り上げる小説は、アイラ・レヴィンの「死の接吻」。1953年作。アイラ・レヴィンの他の作品では「ローズマリーの赤ちゃん」が有名。死の接吻(ハヤカワ・ミステリ ...
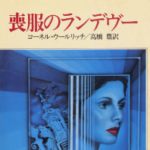
2017/02/23
今回取り上げるのは、コーネル・ウールリッチの「喪服のランデヴー」。コーネル・ウールリッチは、ウィリアム・アイリッシュという筆名でも活躍。「幻の女」「暁の死線」な ...
- パンくずリスト
- ホーム
- ›
- 本
カテゴリー:本