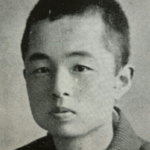Views: 275
入沢康夫の「未確認飛行物体」という詩をご紹介します。
未確認飛行物体
薬罐だって
空を飛ばないとはかぎらない。
水のいっぱい入った薬罐が
夜ごと、こっそり台所をぬけ出し、
町の上を、
心もち身をかしげて、一生けんめいに飛んで行く。
天の河の下、渡りの雁の列の下、
人工衛星の弧の下を、
息せき切って、飛んで、飛んで、
(でももちろん、そんなに早かないんだ)
そのあげく、
砂漠のまん中に一輪咲いた淋しい花、
大好きなその白い花に、
水をみんなやって戻って来る
「未確認飛行物体」が優れている5つの理由
この「未確認飛行物体」という詩は、奇妙である。一読して「これが、詩なの?」と感じた人もおられるだろう。
この「未確認飛行物体」なる詩は、詩として成功しているだろうか。
答えは明瞭だ。これは詩以外の何物でもなく、立派な詩として読者の心を揺り動かすことに成功している。
つまり、良い詩なのだ。
以下、「未確認飛行物体」が良い詩ならしめている要素について解説してみたい。
1)『擬物語詩』というユニークな試み
この「未確認飛行物体」のような詩を『擬物語詩』と呼ぶらしい。
「擬(ぎ)」は「まねる、にせる」という意味。
物語っぽく書いた詩ということか。
通常では、詩とは作者が実際に感じたこと、思ったことを表現する。
要するに、詩においては、嘘はついてはいけない。
しかし、そのルールを、フィクションだっていい、としたらどうか?
架空の物語的な世界を、奇想天外な発想・設定・展開によって描き出し、通常の詩の修辞学では表せない世界、心情、メッセージなどを読者に伝えることができる、と考えて何が悪いのか……という考えから『擬物語詩』は出発しているのだろうと推察する。
2)薬缶が空を飛ぶという「設定」が良い
小説「百年の孤独」で有名なガルシア=マルケスは「想像力のダイナミズム」で以下のように発言している。
「たとえば、象が空を飛んでいると言っても、ひとは信じてはくれないだろう。しかし、4257頭の象が空を飛んでいると言えば、信じてもらえるかもしれない」(『すばる』1981年4月号掲載)
ガルシア=マルケスが描き出した世界は奇想天外、常軌を逸しているが、決して嘘っぽく感じない。
いや、ガルシア=マルケスのつく嘘には、読んだ途端にまるごと信じてしまう、摩訶不思議なリアリティがある。
ガルシア=マルケスの小説を読むと、幻想と現実との境目のない「魔術的リアリズム」世界に酔いしれることができる。
この「魔術的リアリズム」に似た世界が、この「未確認飛行物体」でも現出されている。
まずは何といっても、薬缶に空を飛ばせた設定が良い。
あとは、ガルシア=マルケスばりに、読者を瞬時に自分のペースに巻き込めるかである。
3)ただの薬缶が、愛すべきキャラに
擬人法によって、薬缶がまるで生き物(人)のように、描かれている。
水のいっぱい入った薬罐が
夜ごと、こっそり台所をぬけ出し、
町の上を、
心もち身をかしげて、一生けんめいに飛んで行く。
天の河の下、渡りの雁の列の下、
人工衛星の弧の下を、
息せき切って、飛んで、飛んで、
(でももちろん、そんなに早かないんだ)
決して格好良くはないけれど、どこか鈍くさいところが愛らしい、われらがニューヒーロー「薬缶くん」、あるいは「薬缶ちゃん」の誕生である。
赤字で強調した箇所は、ひたむきで、少し滑稽な「薬缶ちゃん」のキャラクターを巧みに描いている箇所を、赤字で強調してみた。
ところで、「薬缶ちゃん」は、一生懸命に空を飛んで、何をしてようとしているんだろうか?
4)意外な結末
クライマックスをすっ飛ばして、いきなりエンディング。
そのあげく、
砂漠のまん中に一輪咲いた淋しい花、
大好きなその白い花に、
水をみんなやって戻って来る
ドラマチックな結末が描かれず、むしろ「な~んだ、こんなことなの~」とがっかりするくらいにの「オチ」だ。
しかし、この「拍子抜け」こそ、愛すべきキャラの「薬缶ちゃん」にはふさわしい。
偉大なことを成し遂げようとするのではなく、お花に水をやるだけとは、さすがは隣のヒーロー「薬缶ちゃん」である。
5)短い
この「未確認飛行物体」は、予想以上に早く終わってしまう。呆気ないと思うほど、「短い」のである。
この「短い」ことで、嘘が嘘っぽく感じない、とも言えるだろう。
設定やディテール、物語展開に凝りすぎると、無理が生じて、つまらなくなる危険性もある。
だから「短い」方が良かったのだ。
それに、「長い」と説明過多になったり、イメージを限定してしまいかねない。
読者が自由に想像力という翼を広げられるように、「省略」という究極の美学を採用したとも言えそうだ。