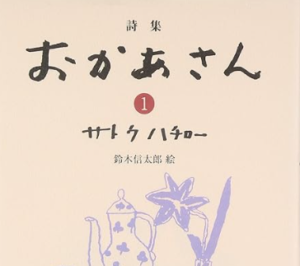今回は、サトウハチローの「ちいさい母のうた」という詩をご紹介します。
ちいさい母のうた
ちいさい ちいさい人でした
ほんとうに ちいさい母でした
それより ちいさいボクでした
おっぱいのんでる ボクでした
かいぐり かいぐり とっとのめ
おつむてんてん いないいないバア
きれいな声の人でした
よく歌をうたう 母でした
まねしてうたう ボクでした
片言まじりのボクでした
ああ アニィローリー マイボニィ
それから ねんねんようおころりよう
羊によくにた人でした
やさしい目をした 母でした
ころころこぶたのボクでした
おはなをならす ボクでした
すぐにおぼえた 午後三時
おちょうだいする くいしんぼう
毎晩祈る人でした
静かに つぶやく母でした
寝たふりしているボクでした
なんだか悲しい ボクでした
春はうるんだ お月さま
秋は まばたきしている星
影絵を切りぬく人でした
うつしてみせる母でした
お手手たたくボクでした
何度も せがむボクでした
外はこまかい 粉の雪
影絵のきそうな白い路
夜なべをしている人でした
よくつぎをあててる母でした
ときどきのぞく ボクでした
よくにらまれる ボクでした
こおろぎ みみずく 甘酒屋
遠い チャルメラ おいなりさーん
話のじょうずな人でした
たくさん知ってる人でした
ソエカヤ?というボクでした
なかなか寝られない ボクでした
エクトロ・マロー アンデルセン
かちかち山に かぐや姫
ああ
思い出の中
その中で
こっちをむいている ちいさい人
ちいさい母
ああ 思い出の中
その中で
なお 甘えている ちいさいボク
ちいさいボク
ちいさい
ちいさい
むかしの
むかしの
むかしのボク
ちいさい………むかしのボク
ちいさい………むかしのボク
豊かだなあ。長いなあ。長いけれども、書き写すのには少し苦労したけど、どうしても書き写したくなる、ほんとにほんとに豊かな詩で……。
それと、何といっても、サトウハチローの詩才の豊かさ。
詩想が、書き出して詩らしき原稿が、完全な詩作品となるために、何が必要なのかを、サトウハチローの詩を読めばよくわかる。
母親をテーマに、このワンテーマで、ここまで喋れる人って、子供って、それ自体が事件だね。奇跡かもしれない。
奇跡だけれど、よくわかる。時代の変化が、日本の変化が、この詩に息づく母親を、子供も、残酷にも、現実社会から消し去ってしまった。
パソコンとか、スマホとかが「おかあさん」を消してしまったのかもしれない。それくらい、ちいさなことが、ささいなことが、この世で最大級に大切なものを、簡単に消してしまうのだろう。
遠い風景。いくら手を差しのべても、想いをめぐらせても、帰ってこない、かけがえのないもの。
そういうものを、そういうことを、想い出すためにしか、詩はあることの無念さよ。
懐かしいなどという生易しい気持ちではない。
「母」が、「おかあさん」が、日本の母親が、詩が、優しさが、温もりがよみがえって来る詩、それが「ちいさい母のうた」、哀しく、寂しいうただ。