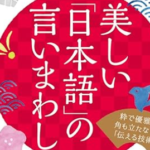- 投稿 更新
- 日本語 - 美しい日本語(言葉)
Views: 9
今回は「たそかれどき(誰そ彼時)」「かはたれどき(彼は誰時)」という二つの日本語を取り上げます。
【動画】「たそかれどき(誰そ彼時)」「かはたれどき(彼は誰時)」について
この2つの日本語は、アニメ映画「君の名は。」で出てくるのです。
「君の名は。」(きみのなは。英: Your Name.)は、2016年に公開された新海誠監督による日本の長編アニメーション映画。
アニメ映画「君の名は。」では「黄昏時(たそがれどき)」の語源として「たそかれどき(誰そ彼時)」をあげ、その意味を「夕方、昼でも夜でもない時間。世界の輪郭がぼやけて、人ならざるものに出逢うかもしれない時間」と説明していました。
「たそがれ」は江戸時代までは「たそかれ」といい、「たそかれどき」の略語です。陽が沈んであたりが暗くなってきて、目の前の人の顔を見ても、誰なのかがわからないくらいの明るさしかない時間帯のことを「誰そ彼時」と呼びます。
「誰そ彼」には「そこにいるのは誰ですか」「誰ですかあなたは」という意味が込められているのです。
「たそかれどき」の語源を学んでいると、何だか、気持ちがほっこりしてきますね。陽が沈んで暗くなり、人の顔がよくわからなくなるくらいの明るさの時間帯を、実に情感豊かな言葉で日本人は表現してきたのですね。
「たそかれどき(誰そ彼時)」は日没後を指しますが、夜明け前のことは「かはたれどき(彼は誰時)」といいます。
しかし、現在では、この「かはたれどき(彼は誰時)」は使われなくなり、「たそがれどき」とだけ使われるようになりました。
「たそかれどき(誰そ彼時)」と「かはたれどき(彼は誰時)」は、幻想的で美しいし、色彩と温もりが感じられる、素晴らしい日本語ですね。
言葉が単なる記号ではなく、体温を感じる「ことのは」であることに気づく、そのきっかけを「たそかれどき」「かはたれどき」という言葉を与えてくれている気がします。
逆にいいますと、「たそかれどき」という言葉を使わなくなるということは、そうした微妙な情感を失ってしまったことの証明でもあるのです。
これは、怖いことですね。
現在では「黄昏(たそがれ)」と言いますが、これでは繊細な情緒が感じられませんよね。