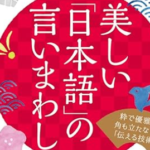
2024/03/05
「もののあはれ」という言葉を説明しようとすると、言葉に詰まってしまうのではないか。「もののあはれ」とは何か、と問われた時に、即答できる人は多くはないだろう。そう ...
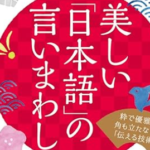
2019/08/17
夏まっさかりですね。この季節になると、美しいひとつの日本語が感じられるようになります。それは「蝉時雨(せみしぐれ)」。大辞林は以下のように「蝉時雨」を説明してい ...

2019/07/10
「風花未来(かざはなみらい)」って、変わった名前ですね、とよく言われます(苦笑)。名前がきれいすぎるのか、女性と間違えられることも少なくありません。実際は、男性 ...

2019/06/17
日本語 - 美しい日本語(言葉) - 詩心回帰・まどか - 言葉の力で暮らしを変える
私が「言葉を暮らしのまん真ん中にすえること」を決意したのは、他の表現方法に対し、失望したというか、諦めてしまったからです。例えば、映像文化。次々に動画に関わる技 ...
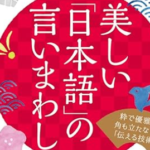
2019/06/01
いちばん好きな日本語を一つだけ選べと言われたら「しなやか」をあげるかもしれません。想いかえせば、この「しなやか」という言葉の美しさ、いえ、その「強さ」を知ったの ...
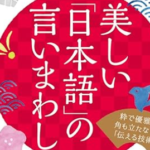
2019/05/26
「しずもり」という言葉は、私(風花未来)の造語(オリジナルワード)です。日本語には、ラ行五段活用の動詞「鎮もる」「静もる」の連用形である「鎮もり」「静もり」、あ ...
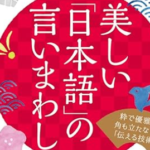
2019/05/25
美しい日本語(美しい日本の言葉)の約50例の記事をここにまとめてみました。日本語の美しさ、豊かさをご堪能いただけたら幸いです。「言葉への愛は、人への愛」に通じて ...
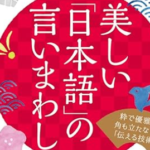
2019/05/25
「美しい言葉」「美しい日本語」について語ろうとする時、いつも思うのは、言葉は時代とともに変わる、そして、人とともに変わることです。言葉は人間が生み出し、人間が使 ...
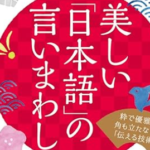
2019/05/19
私の好きな言葉に「心眼(しんがん)」があります。「心眼」という言葉の深さを私に教えてくれた人は、二人います。デットマール・クラマー、松本育夫です。松本育夫は、元 ...

2019/05/18
「目は心の窓」という諺(ことわざ)は英語にもあります。Theeyeisthewindowoftheheart.(目は心の窓)似た言葉に「目は心の鏡」がありますが ...
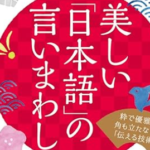
2019/04/30
日本語 - 美しい日本語(言葉) - 言葉の力で暮らしを変える - 言葉による引き寄せ
「平成」を振り返ることで、「令和」を希望の時代にするためのヒントを、YouTubeで語ることで探ってみました。1時間弱の音声ですが、よろしかったら、お聴きくださ ...
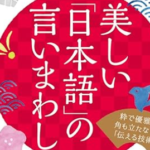
2019/04/29
以前、当ブログ「美しい言葉」で「美しい日本語ベスト10」という記事を投稿したことがあります。⇒美しい日本語ベスト10上のリンク先の結果は、NHKのアンケートによ ...

2019/04/01
本日、平成31年(2019年)4月1日に、新元号が発表されました。平成の次の元号は「令和(れいわ)」に決定。今日はあくまで新元号が発表されただけで、元号が平成か ...
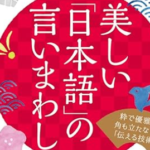
2019/03/22
「身土不二」という言葉をご存知でしょうか。仏教用語では「しんどふに」と読み、食養用語では「しんどふじ」と読みます。この少しミステリアスな言葉を、私は「チャンネル ...
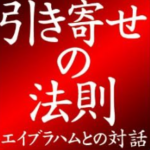
2019/01/09
日本語 - 美しい日本語(言葉) - 言葉の力で暮らしを変える - 言葉による引き寄せ
毎日発する言葉によっても、引き寄せの法則は作用します。引き寄せに働くのは思考や感情だけではありません。話す言葉も引き寄せのパワーを生む波動や磁力に大きな影響を及 ...
カテゴリー:美しい日本語(言葉)