カテゴリー:草野心平
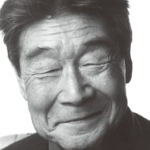
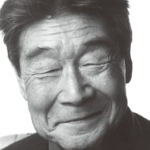
2024/03/10
草野心平の「空間」という詩をご紹介しよう。空間中原よ地球は冬で寒くて暗い。ぢやさやうなら。「中原」は詩人の中原中也を指す。中原中也は1937年(昭和12年)に、 ...
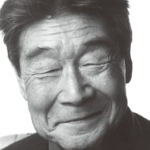
2021/12/08
草野心平の「秋の夜の会話」という詩をご紹介します。秋の夜の会話さむいねああさむいね虫がないてるねああ虫がないてるねもうすぐ土の中だね土の中はいやだね痩せたね君も ...
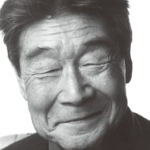
2021/06/14
草野心平の「青イ花」という詩をご紹介します。青イ花トテモキレイナ花。イッパイデス。イイニホヒ。イッパイ。オモイクラヰ。オ母サン。ボク。カヘリマセン。沼ノ水口ノ。 ...
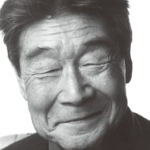
2019/08/16
今回は、草野心平(くさのしんぺい)の詩を取り上げます。草野心平は1903年(明治36年)5月12日生まれ。1988年(昭和63年)11月12日に死去した日本の詩 ...