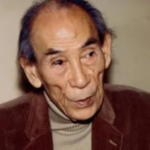Views: 17

真昼の星群──幼い日の光景をめぐって
こんにちは、風花未来です。
今日は、私の詩「真昼の星群」について、少しだけお話しさせてください。
詩を書くとき、私はいつも“心の奥に沈んでいるもの”にそっと触れようとします。
それは、誰にも言えなかった幼い日の記憶であったり、言葉になる前の感情であったり、あるいは、ふとした瞬間に胸の奥で震える光のようなものだったりします。
「真昼の星群」は、そんな“言葉になる前の記憶”を、長い年月を経てようやく掬い上げた詩です。
幼い日の私は、世界の輪郭がまだ曖昧で、現実と夢の境界がゆるやかに溶け合っていました。
その曖昧さは、恐れでもあり、同時に、世界の美しさをそのまま受け取れる透明さでもありました。
この詩は、その頃の私が見た“真昼の星”の記憶をめぐるものです。
それが本当にあった出来事なのか、あるいは夢だったのか──
今となっては確かめようもありません。
けれど、あの光景が胸に残した震えだけは、今もはっきりと覚えています。
では、まずは詩をそのままお読みください。
真昼の星群
あの晴天の午後
暗い部屋の小さな窓から
幼いわたしはひとり
真っ青な空に
無数の星を見た
いつもいっしょに
小さな窓から外を眺める
兄はその日はいなかった
真昼に星を見たのは
初めてだった
鋭い叫び声が聞こえたが
それはわたし自身の声にならない叫びだった
声にならない叫びを
小さな胸の奥に飲みこんだまま
わたしはその日
うれしいような
こわいような
そんな気持ちで
ふるえながらすごした
晴天の午後に見た星のことは
誰にも言わなかった
その日のことを
何十年も経った
今おもいだすと
ほんとうに真昼の星群を見たのか
それとも夢だったのか
わからなくなる時がある
あの時のわたしは
狂っていたのか
それとも正気すぎて
冴えかえった心の眼に
蒼穹の星が映ったのか
ただ忘れようもないのが
あの無数の星ぼしの
こわいほどの
鮮やかさ
うつくしさ
あの確かさは
たとえ夢だとしても
あれほど
はげしく
狂おしい
光景は見たことがない
とおいとおい
幼い日の記憶である
詩の奥にあるもの──“こわいほどの美しさ”について
この詩を書いたとき、私は“美しさ”というものの本質を考えていました。
美しさは、ただ優しいだけのものではありません。
ときに、胸を刺すような鋭さを持ち、ときに、心の奥を震わせるほどの強さを持ちます。
幼い日の私は、その“こわいほどの美しさ”に触れてしまったのだと思います。
それは、世界の秘密を少しだけ覗いてしまったような、そんな感覚でした。
そして、あの星々の光景は、私が詩人として歩む道のどこか深いところで、
ずっと灯り続けている小さな星のようなものです。
記憶は、時に夢よりも曖昧で、時に夢よりも確か
長い年月が経つと、記憶は静かに形を変えていきます。
けれど、変わらず残るものがあります。
それは、出来事そのものではなく、その瞬間に胸に宿った“感情の震え”です。
「真昼の星群」は、その震えを、言葉という形でそっとすくい上げた詩です。
もしあなたの心にも、幼い日の“誰にも言えなかった光景”があるなら、この詩がその記憶にそっと寄り添うことができたら、私はとても嬉しく思います。