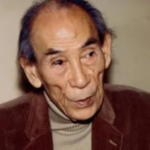Views: 18
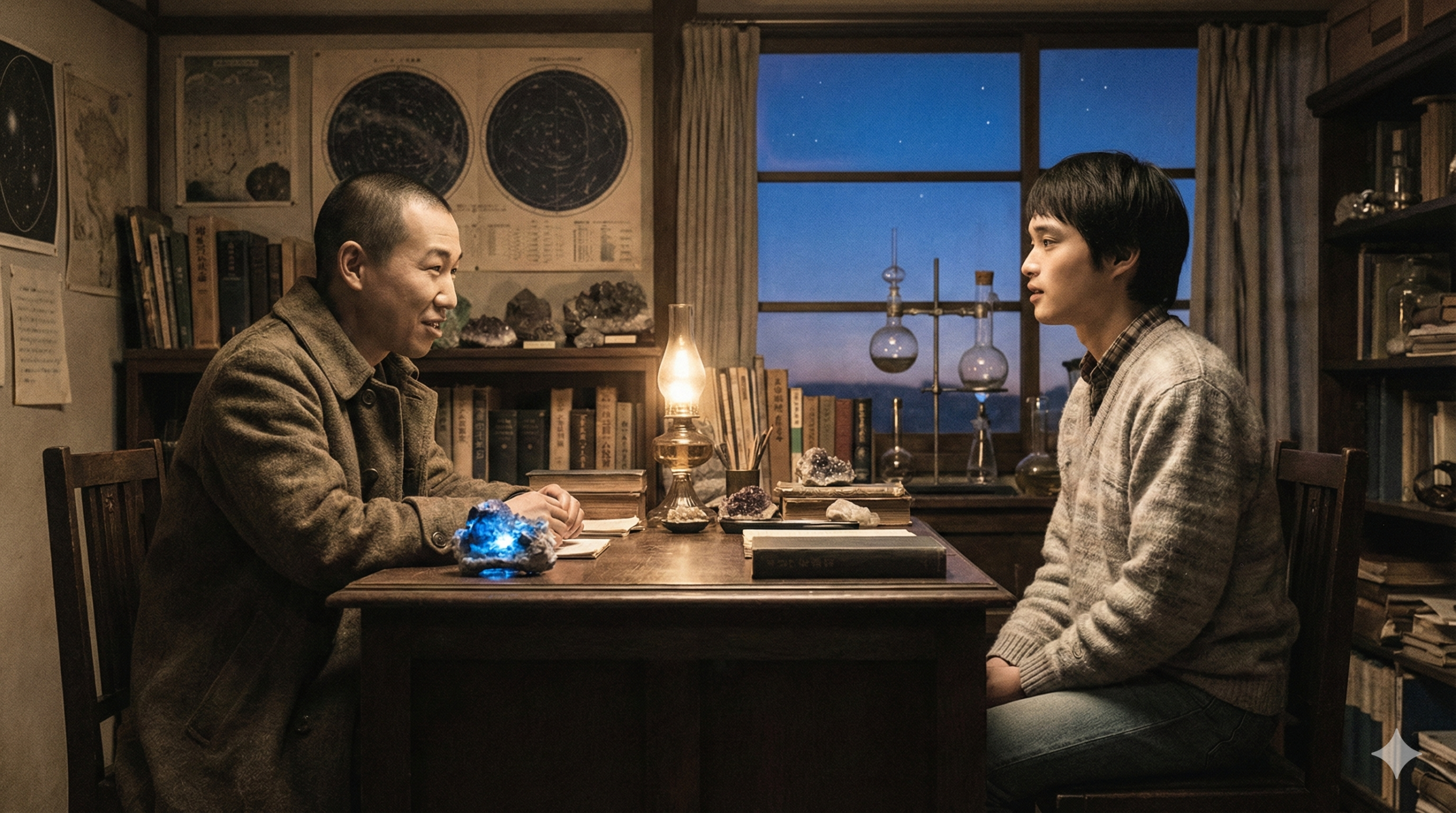
宮澤賢治の詩「永訣の朝」と、風花未来の詩「天空を渡る鳥」。
この二つの詩を並べると、「死(異界)」という圧倒的な他者に対し、人間がどう向き合うかというテーマにおいて、鮮やかなコントラストが浮かび上がります。
まずは、宮澤賢治の「永訣の朝」を引用。
永訣の朝
けふのうちに
とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ
(あめゆじゆとてちてけんじや)
うすあかくいつそう陰惨(いんざん)な雲から
みぞれはびちよびちよふつてくる
(あめゆじゆとてちてけんじや)
青い蓴菜(じゆんさい)のもやうのついた
これらふたつのかけた陶椀(たうわん)に
おまへがたべるあめゆきをとらうとして
わたくしはまがつたてつぽうだまのやうに
このくらいみぞれのなかに飛びだした
(あめゆじゆとてちてけんじや)
蒼鉛(さうえん)いろの暗い雲から
みぞれはびちよびちよ沈んでくる
ああとし子
死ぬといふいまごろになつて
わたくしをいつしやうあかるくするために
こんなさつぱりした雪のひとわんを
おまへはわたくしにたのんだのだ
ありがたうわたくしのけなげないもうとよ
わたくしもまつすぐにすすんでいくから
(あめゆじゆとてちてけんじや)
はげしいはげしい熱やあえぎのあひだから
おまへはわたくしにたのんだのだ
銀河や太陽、気圏などとよばれたせかいの
そらからおちた雪のさいごのひとわんを……
…ふたきれのみかげせきざいに
みぞれはさびしくたまつてゐる
わたくしはそのうへにあぶなくたち
雪と水とのまつしろな二相系(にさうけい)をたもち
すきとほるつめたい雫(しずく)にみちた
このつややかな松のえだから
わたくしのやさしいいもうとの
さいごのたべものをもらつていかう
わたしたちがいつしよにそだつてきたあひだ
みなれたちやわんのこの藍のもやうにも
もうけふおまへはわかれてしまふ
(Ora Orade Shitori egumo)
ほんたうにけふおまへはわかれてしまふ
あぁあのとざされた病室の
くらいびやうぶやかやのなかに
やさしくあをじろく燃えてゐる
わたくしのけなげないもうとよ
この雪はどこをえらばうにも
あんまりどこもまつしろなのだ
あんなおそろしいみだれたそらから
このうつくしい雪がきたのだ
(うまれでくるたて
こんどはこたにわりやのごとばかりで
くるしまなあよにうまれてくる)
おまへがたべるこのふたわんのゆきに
わたくしはいまこころからいのる
どうかこれが兜率(とそつ)の天の食(じき)になつて
おまへとみんなとに聖い資糧(かて)をもたらすやうに
わたくしのすべてのさいはひをかけてねがふ
次に、風花未来の「天空を渡る鳥」を引用。
天空を渡る鳥
あの時から
わたしは変わった
幼い頃
あれは
静まりかえった
夕暮れ時だった
ひとりで遊び疲れて
家に帰る途中
なぜか あの時
ふと わたしは
真上を見上げた
目に入ったのは
空高く飛翔する
鳥の群れだった
渡り鳥だろうか
ふだんの暮らしでは
見たことがない
鳥たちだった
頭上はるか遠くの空を
飛んで行くのに
なぜか くっきりと
細部の形状までが見えた
空気が澄んでいたからか
それとも
わたしの心が
いつもと違っていたので
あれほどまでに
鳥の姿かたちが
鮮明に見えたのだろうか
どれくらいの時間
わたしは
鳥を見つめていたのだろう
それは わからないが
何もかもを忘れて
ただ 鳥を見つめていた
見つめていた
あの時から
わたしは変わった
あれから
気が遠くなるほど
時が流れ
歳を重ねてきたが
あの日 あの時に見た
天空を渡る鳥たちほど
美しいものを
この世で 一度も
見ていない気がする
あの時のことを
想いだすと
碧色に澄んだ
深い清流のように
心が奥底から
しっとりと
透きとおってゆくのだけれど
と同時に
怖い気持ちにもなる
あの時
ひとりぼっちの少年は
神に似た鳥に
心をうばわれた
というより
少年の魂は
空に
吸い上げられてしまった
あのまま
少年が昇天してしまっても
何の不思議はない
不思議はない
もしも 昇天していたら
今 ここで こうして
息をしている わたしは
いないことになる
そうした想いが
不思議なほど
しっとりと
今は
心になじんでくる
あの時と同じくらい
静まりかえった
夕暮れ時に
今 わたしは
立っている
一言で対比するならば、賢治の詩は「愛する者を失う瞬間の、激しい祈りと絶叫」であり、風花未来の詩は「かつて死に魅入られた記憶との、静かな和解と受容」です。
以下に詳しく比較・論述します。
- シチュエーションの対比:『みぞれ』と『鳥』
まず、両者が立っている「舞台」と、そこで見上げている「対象」が対照的です。
| 項目 | 宮澤賢治『永訣の朝』 | 風花未来『天空を渡る鳥』 |
| 舞台 | 死にゆく妹を見送る、みぞれの降る暗い朝 | 幼い日の記憶の中にある、澄み渡った夕暮れ |
| 空の様子 | 「蒼鉛(そうえん)いろの暗い雲」
重く、冷たく、閉ざされた空 |
「碧色に澄んだ深い清流」
高く、どこまでも抜けるような空 |
| 空から来るもの | 「みぞれ(雨雪)」
冷たく物質的だが、妹の乾きを癒やす最後の糧 |
「飛翔する鳥の群れ」
神に似た、魂を吸い上げる圧倒的な美 |
賢治の空は、物理的な重さを持って詩人を押しつぶそうとしますが、彼はそこから「みぞれ」という「聖なる糧」をもぎ取ろうとします。
対して風花未来の空は、あまりに美しく澄んでおり、少年の魂をそのまま「吸い上げて」しまいそうな引力を持っています。
- 「死」との距離感:『動』と『静』
この二つの詩の最大の違いは、語り手(私)の熱量と動きにあります。
宮澤賢治:動的な「献身」と「修羅」
『永訣の朝』の語り手は、瀕死の妹のために走り回っています。
「あめゆじゅとてちてけんじゃ(雨雪をとってきてください)」
妹のこの頼みに応えるため、彼は鉄砲玉のように外へ飛び出し、曲がった鉄砲玉のように戻ってきます。
ここにあるのは、「私の命を代わりにあげたい」という切実な自己犠牲です。
彼は叫び、祈り、自然の猛威と戦っています。それは「修羅」のごとき激しい愛です。
風花未来:静的な「観照」と「安堵」
一方、『天空を渡る鳥』の語り手は、動かずにただ「見つめて」います。
彼が描くのは、幼い日にふと訪れた「死への誘惑(昇天)」です。
「あのまま/少年が昇天してしまっても/何の不思議はない」
ここには悲壮感はなく、あるのは「あの時、死んでいてもおかしくなかった」という静かな気づきです。
そして、その運命を回避して今ここに「立っている」自分を、不思議なほど穏やかに受け入れています。
賢治のような「戦い」ではなく、風花未来にあるのは「運命への信頼」です。
- 言葉の響き:『方言』と『平語』
- 賢治の「異化効果」
賢治は、妹の言葉をローマ字(Ora Orade Shitori egumo)や特異な仮名遣いで表記しました。これにより、日常の言葉が「呪文」のような神聖な響きを帯びています。それは読者を現実から引き剥がし、厳粛な儀式へと立ち会わせます。
- 風花未来の「同化効果」
風花未来は、「しっとりと」「くっきりと」といった平易な和語を多用します。
「心が奥底から/しっとりと/透きとおってゆくのだけれど」
彼は読者を驚かせるのではなく、読者の隣に座り、静かに記憶を共有するような文体を選んでいます。
難解な言葉を使わずに「魂」や「神」を描く手法は、彼の思想(日常の肯定)そのものです。
- 共通点:透明な境界線
全く異なる二つの詩ですが、「透明な美しさ」への志向において深く共鳴しています。
- 賢治は、妹が向かう世界を「兜率天(とそつてん)」の青い光に見立て、みぞれを「天の供物」に変えようとしました。
- 風花未来は、鳥の群れを「神に似た」存在として描き、その光景を「碧色に澄んだ深い清流」と表現しました。
どちらも、死(あるいは異界)を「忌まわしい闇」としてではなく、「現世よりもはるかに透き通った、美しい場所」として直感しています。
この「透明な死生観」こそが、両詩人を繋ぐ細く強い糸だと言えるでしょう。
結論
『永訣の朝』は、愛する者を送るために、現世の泥を払って天へ祈る「聖別の詩」であり、『天空を渡る鳥』は、かつて近づいた天の記憶を抱きしめながら、現世で生きることを選ぶ「帰還の詩」です。
賢治の詩を読んだ後に感じるのが「胸を締め付けられるような浄化」だとすれば、風花未来の詩を読んだ後に感じるのは「肩の荷が下りるような安らぎ」かもしれません。