Views: 7
正岡子規(まさおかしき)の有名な短歌に「瓶にさす 藤の花ぶさ みじかければ たたみの上に とどかざりけり」があります。
正岡子規の有名な短歌と申しましたが、2019年の現在において、知らない人もかなり多いでしょうね。
先日、二十代の人たちと話す機会があったのですが、「高村光太郎」を知っている人がほとんどいませんでした。
とんでもない時代になったものです。よいものはよいものとして、しっかり伝えてゆかないと、私たち日本人の心はますます貧困になってしまう気がしてなりません。
ということで、正岡子規のこの短歌は知っていて当たり前ということは、現代社会ではもう通用しないと知った上で、この短歌について語ってみたいと思います。
正岡子規(1867年10月14日~1902年)は、日本の俳人、歌人、国語学研究家。夏目漱石の親友であったことは有名。
正岡子規は34歳で死ぬまでの約7年間、結核で病床にふしておりました。「瓶にさす」の歌が歌われた時は、寝返りも打てない状態だったらしい。
短歌の鑑賞から、私自身、遠ざかっていたのですが、中野好夫の「文学の常識」という本を読んでいて、正岡子規の「瓶にさす 藤の花ぶさ みじかければ たたみの上に とどかざりけり」を見つけたのでした。
「瓶」は「かめ」と読みます。
中野好夫はこの正岡子規の短歌を「非常に良い歌」だとしながらも、具体的な解説や注釈はいっさいしていません。
そこで、何度も何度も口ずさみながら、私なりに意味を取ろうとしてみました。
「瓶にさす 藤の花ぶさ みじかければ たたみの上に とどかざりけり」は「墨汁一滴」という随筆に収められております。「墨汁一滴」は、1901(明治34)年に「日本」に164回にわたり掲載されました。
明治34年は、正岡子規が死去する前年です。
では、「瓶にさす」が歌われている日の記録(全文)を引用してみましょう。
夕餉したため了りて仰向に寝ながら左の方を見れば机の上に藤を活けたるいとよく水をあげて花は今を盛りの有様なり。艶えんにもうつくしきかなとひとりごちつつそぞろに物語の昔などしぬばるるにつけてあやしくも歌心なん催されける。この道には日頃うとくなりまさりたればおぼつかなくも筆を取りて
瓶にさす藤の花ぶさみじかければたゝみの上にとゞかざりけり
瓶にさす藤の花ぶさ一ふさはかさねし書の上に垂れたり
藤なみの花をし見れば奈良のみかど京のみかどの昔こひしも
藤なみの花をし見れば紫の絵の具取り出で写さんと思ふ
藤なみの花の紫絵にかゝばこき紫にかくべかりけり
瓶にさす藤の花ぶさ花垂たれて病の牀に春暮れんとす
去年こぞの春亀戸に藤を見しことを今藤を見て思ひいでつも
くれなゐの牡丹ぼたんの花にさきだちて藤の紫咲きいでにけり
この藤は早く咲きたり亀井戸かめいどの藤咲かまくは十日まり後
八入折やしおおりの酒にひたせばしをれたる藤なみの花よみがへり咲く
おだやかならぬふしもありがちながら病のひまの筆のすさみは日頃稀なる心やりなりけり。をかしき春の一夜や。(四月二十八日)
この短歌には引用したとおり、少し長い前書き(詞書)がつけられております。それを読みますと、どういう状況下でこの短歌が詠まれたのかがよくわかるのです。
横になっていて、ふと左の方を見ると、机の上に藤の花が瓶に活けてあり、水をよく吸い上げて今が盛りのようで「艶にもうつくしきかな」と正岡子規は詠嘆するのです。
この「瓶にさす 藤の花ぶさ みじかければ たたみの上に とどかざりけり」にはいろんな解釈がありまして、それらはネットでも読むことができます。
「藤」を「不治」あるいは「不死」に、「瓶」を「鶴は千年亀は万年」の「亀」に掛けている、いわゆる「掛詞」の手法を使っているという説があるようです。
また藤の花房の短さから、自分の命の短さを思っているという解釈もあるらしい。正岡子規は34歳で亡くなっているので、確かに短命と言えますね。
私もいろいろ考えたのですが、細かい解釈はこの歌に関しては必要ないという結論に達しました。
掛詞とか「短い」とかいうことは、この短歌の評価を上げる理由にはならないと思うのです。
短命な詩人はたくさんいます。しかし、正岡子規ほど「死」を長いこと見つめた人は少ないでしょう。
「死」を正視するからこそ「生」が実感できる。そうした緊張感の中では、感覚が研ぎ澄まされ、観察眼も鋭くなる。「死」と「生」を同時に感じるからこそ、藤の色の鮮やかさがいっそう際立って目に映る。
正岡子規の俳句に「鶏頭の十四五本もありぬべし」がありますが、鶏頭の「赤」実に鮮やかです。
生と死。萎びてゆく自分の命とは正反対のみずみずしい藤の花の色。それらを、感情を表出せずに、淡々と写生したところに、この短歌の美点があるのだと思います。
その美しさは、詮索を排して、素直に読むことでしか味わえないのではないでしょうか。
シンプルで素直なところが、この歌のパワーなのですから。

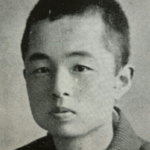

藤の花が満開の今は、一年でもっとも清々しい新緑の季節です。家から出て花を愛でながら散歩している時、ふと子規の歌が脳裏に浮かび健康のありがたみを感じるとともに、伏せってもなお季節のうつろいに心を寄せる精神の自由さを感じました。